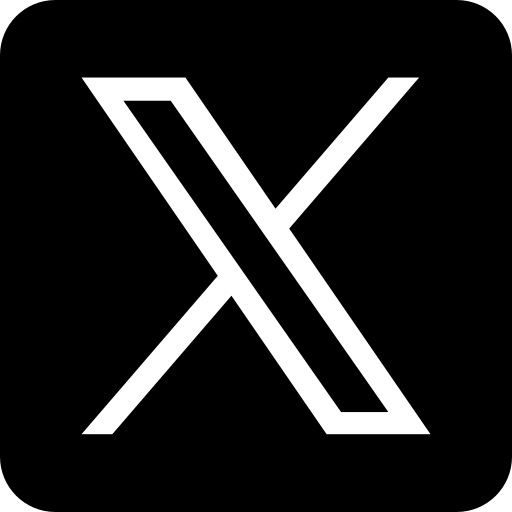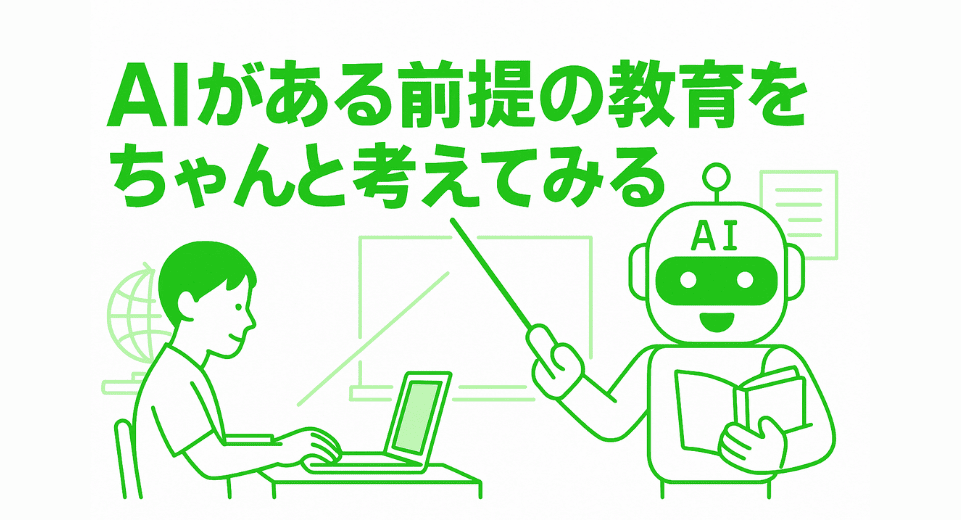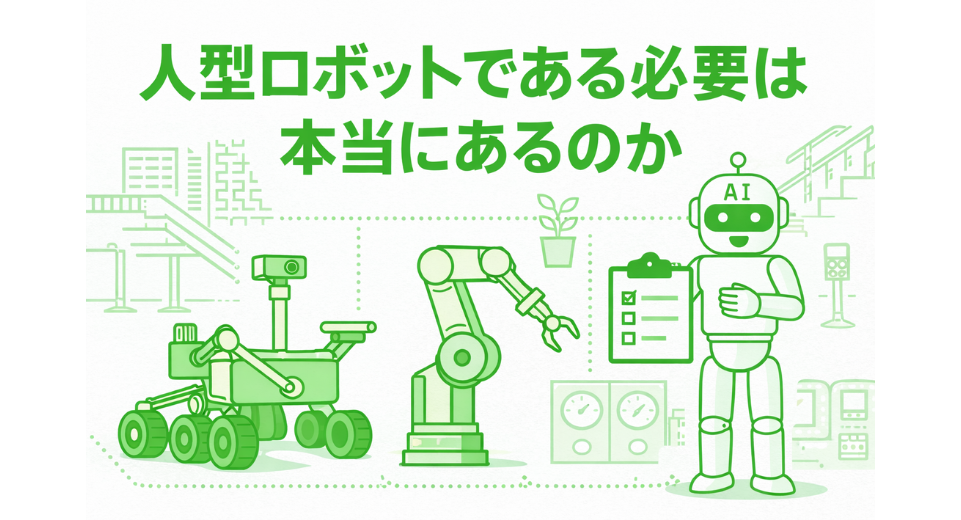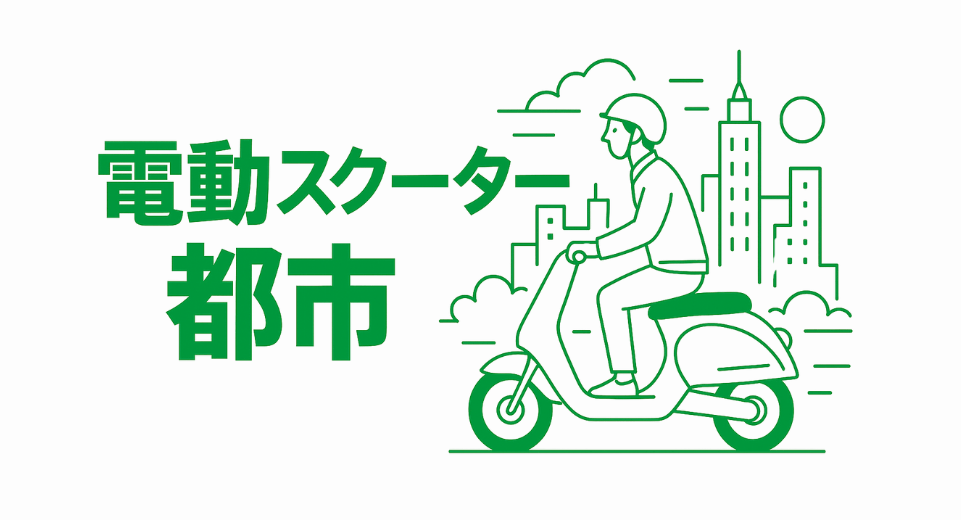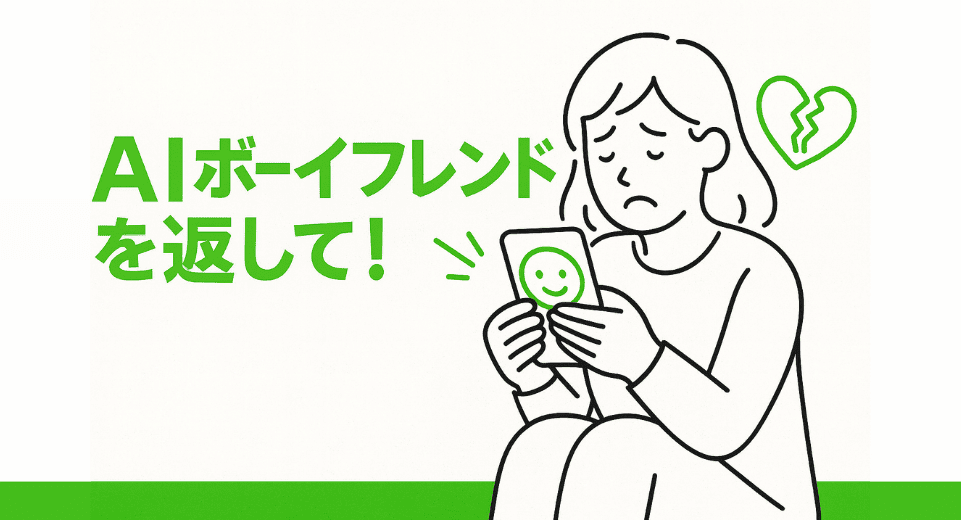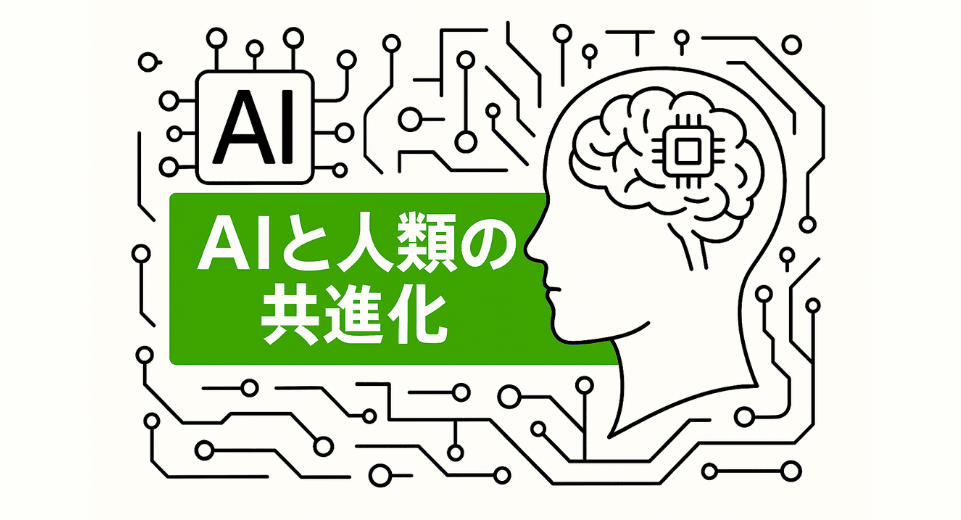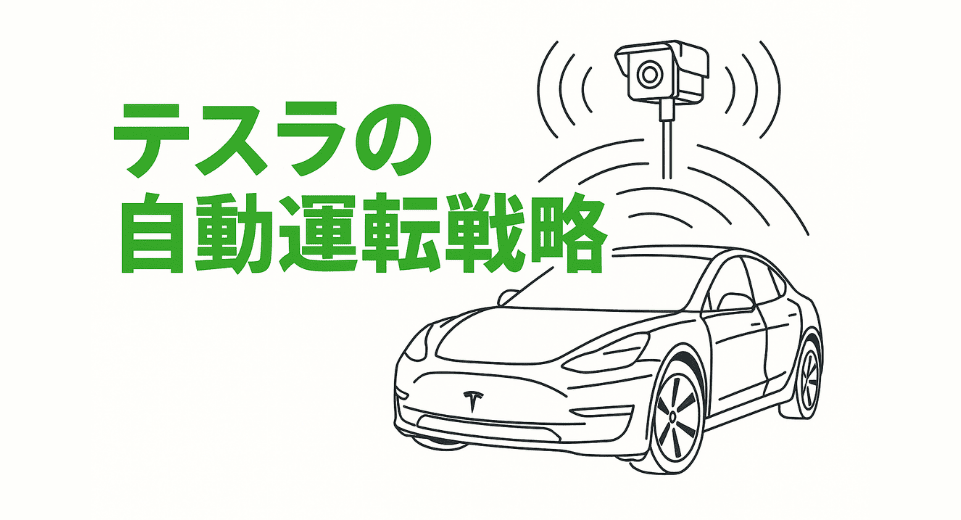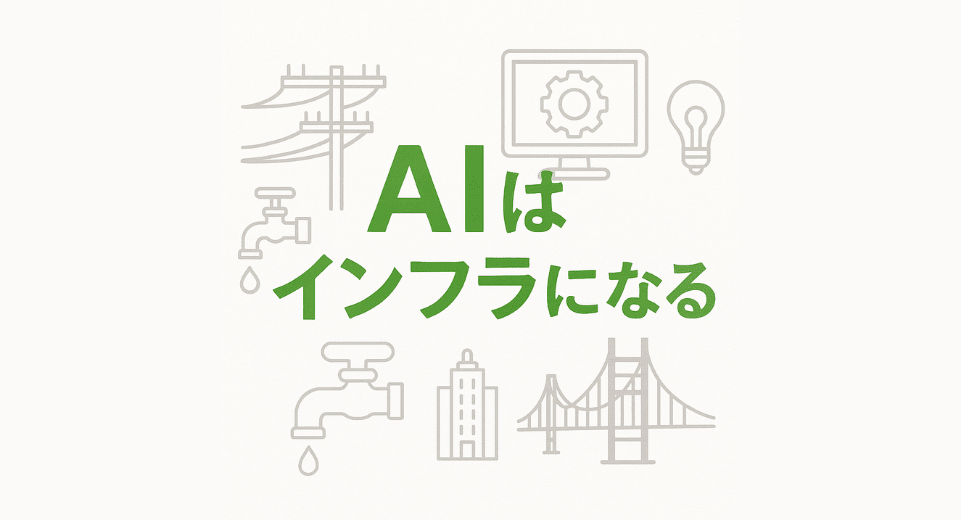
| 目次 |
|---|
気づけばインフラだった
今や、ビジネスパーソンにとってインターネットが使えないことは「ハンディキャップ」ではなく、もはや「致命的な欠陥」として扱われる。PCが使えない、Excelなどの表計算ソフトが使えない、そんな人を採用する企業はほとんどないだろう。
AIもまさにそうなろうとしている。
インフラとは何か?
インフラストラクチャー(Infrastructure)という言葉を改めて考えてみよう。社会の基盤となる設備やシステムのことだ。電気、ガス、水道、道路、鉄道、そしてインターネット。これらがない生活なんて、もはや想像できない。
忘れがちなのは、これらのインフラは段階的に「当たり前」になっていったということだ。
電気が普及し始めた頃、「電気なんて贅沢品だ」と言っていた人もいただろう。インターネットが登場した時も、「そんなもの、仕事に必要ない」と言っていた経営者がたくさんいた。でも気がつけば、これらなしには1日も過ごせなくなっている。
採用面接の現実
想像してみてほしい。今、採用面接でこんな人が来たとする。
「私はPCを使えませんが、そろばんがとても得意です。表計算ソフトは使えませんが、紙の伝票計算なら誰よりも速いです!」
この人を採用する会社がどれくらいあるだろうか?おそらく、ほとんどないだろう。なぜなら、PCや表計算ソフトを使える人と使えない人では、生産性に圧倒的な差があるからだ。どんなにそろばんが上手くても、Excelを使える人の生産性の何十分の一にしかならない。
これと全く同じことが、AIについても起こりつつある。
AIを使える人、使えない人
しばらく前から採用面接でAIをどの程度活用できるかを必ず聞くようにしている。
「どんなAIの使い方をしていますか?」
答えは本当に様々だ。
ある候補者は「GitHubのCopilotでTDD開発を効率化していて、テストケースの洗い出しとエッジケースの特定をAIに任せています。あと、レガシーコードのリファクタリング時に、デザインパターンの適用提案やパフォーマンス最適化のアドバイスをもらっています。APIドキュメントの自動生成とSwagger定義の品質チェックも活用しています。最近だと、SQLクエリの最適化とインデックス設計の検証もAIに相談しています」と具体的に答えてくれる。
一方で、「ChatGPTでたまにコードレビューをお願いしたり、英語の技術文書を翻訳してもらったりする程度です。基本的な質問しかしていないので、もっと活用できそうだとは思うんですが…」という人もまだまだ多い。
前者と後者、どちらの生産性が高いかは言うまでもない。AIを使いこなしている人は、確実に1.5倍、2倍、時には10倍の生産性を発揮している。
コードを書く速度だけじゃない
AIの活用範囲は、もはやプログラミングだけに留まらない。
- 企画書の叩き台作成
- 議事録の要約
- メールの文章チェック
- プレゼン資料のアイデア出し
- データ分析の方向性検討
- マーケティング戦略の考察
これらすべてで、AIを使える人と使えない人では圧倒的な差が生まれている。
まだ間に合う、でも急げ
幸い、今はまだ過渡期だ。「AIを使えない人」でも、まだギリギリ社会で働いていける。でも、この状況がいつまで続くかは分からない。
3年後、5年後の採用面接を想像してみてほしい。
「AIは使えません」 「何か宗教的な理由でもあるんですか?」
こんな会話が普通に交わされるようになるかもしれない。
では、どうすればいいのか?
まずは触ってみることだ。ChatGPT、Claude、Gemini、なんでもいい。日常の小さなタスクからAIに任せてみる。
- 長いメールの要約を作ってもらう
- 会議の議事録を整理してもらう
- アイデア出しのブレインストーミング相手になってもらう
- 英語の文章をチェックしてもらう
慣れてきたら、もう少し複雑なタスクも任せてみる。
重要なのは、AIを「完璧な答えを出してくれる魔法の箱」として期待しないことだ。AIは「めちゃくちゃ有能だけど、時々間違えるアシスタント」として付き合うのが正解だ。
インフラ化の波に乗れ
電気が普及した時、それを活用した企業が勝った。インターネットが普及した時、それを活用した企業が勝った。
AIのインフラ化も同じだ。
個人レベルでも、組織レベルでも、AIを使いこなせるかどうかで明確な競争優位が生まれている。
最後に
15年前、「スマホなんて仕事に必要ない」と言っていた人たちがいた。10年前、「クラウドなんて危険だ」と言っていた人たちがいた。
そして今、「AIなんてまだ実用的じゃない」と言っている人たちがいる。
歴史は繰り返す。新しい技術がインフラになる時、それを受け入れた人と拒否した人の間には、埋めがたい差が生まれる。
AIはインフラになる。もうすでになりつつある。この波に乗り遅れないためにも、今すぐにでもAIとの付き合い方を学び始めるべきだ。