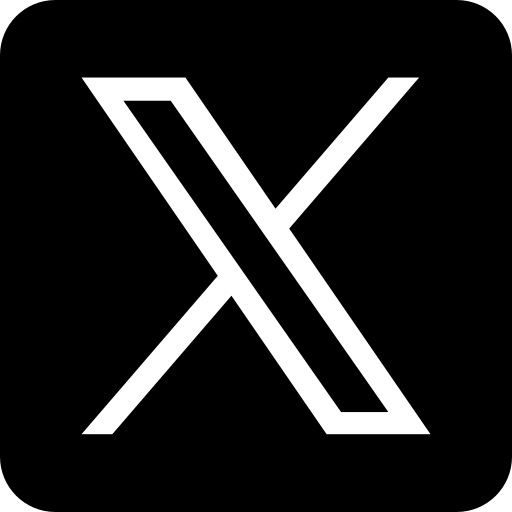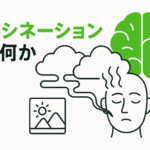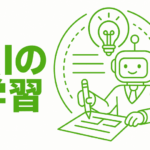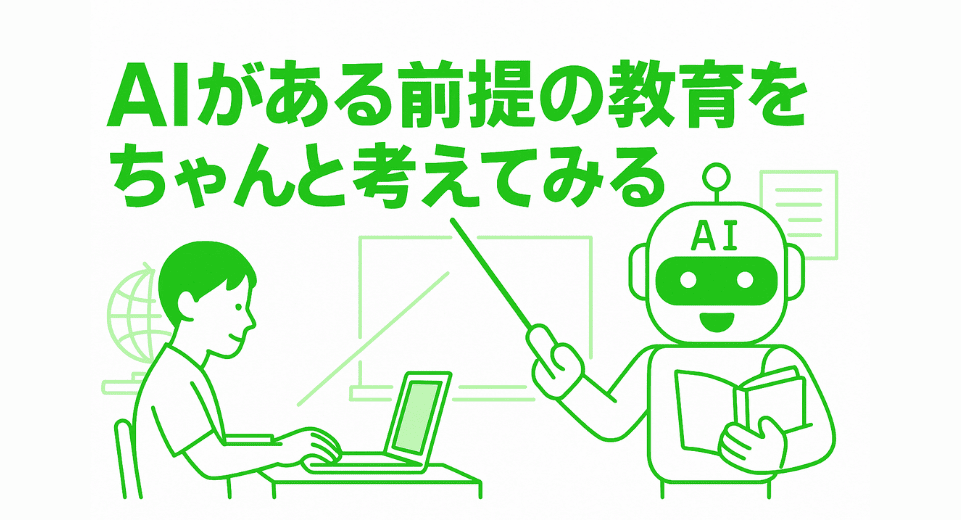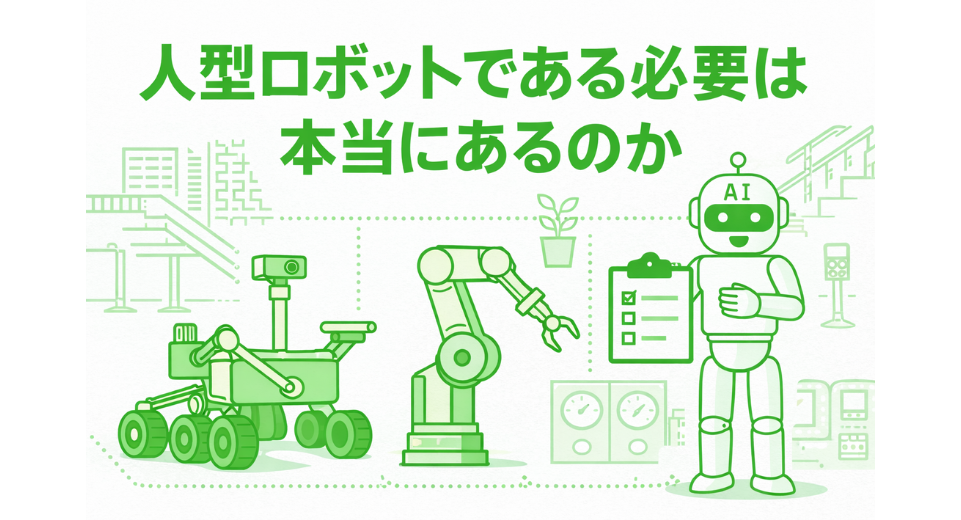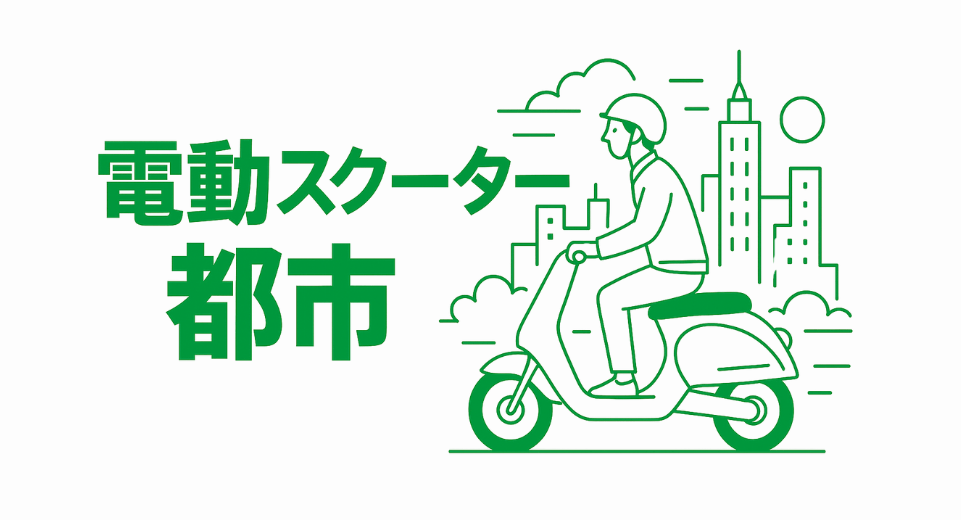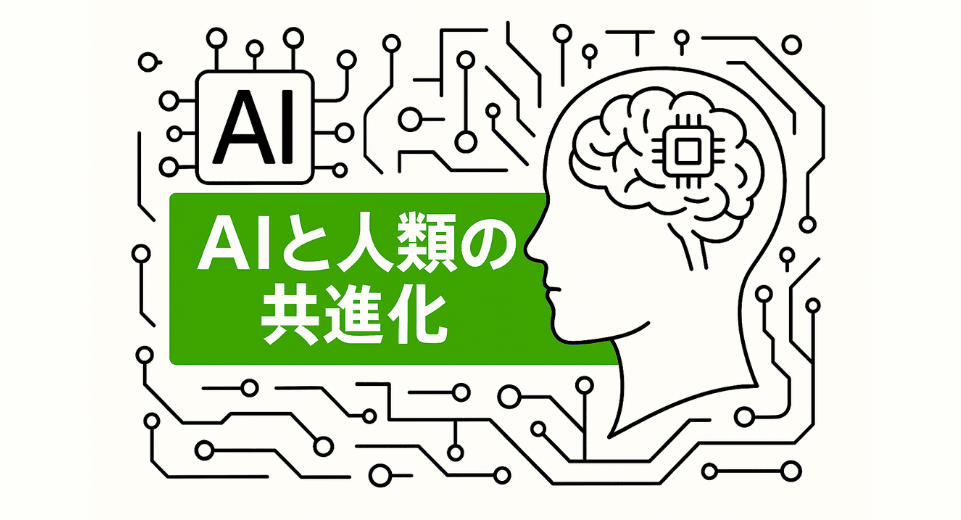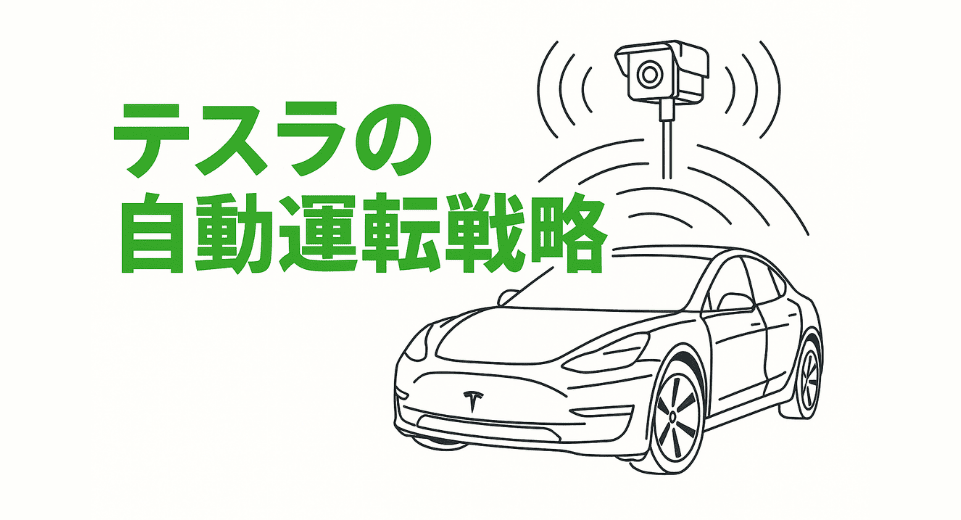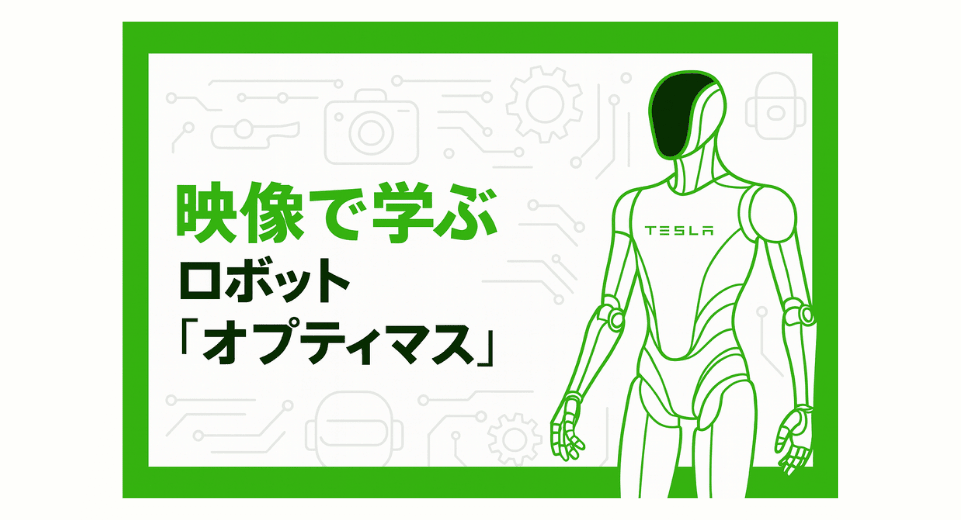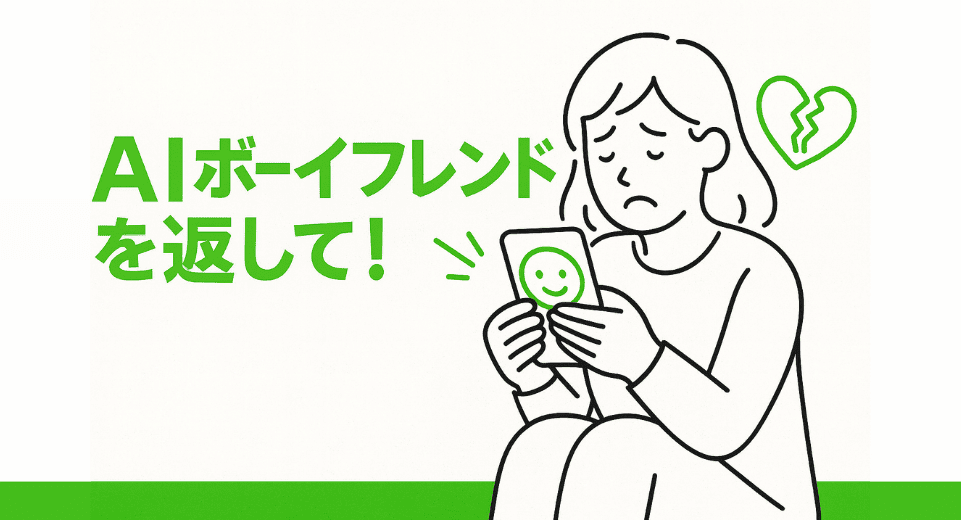
| 目次 |
|---|
GPT-5登場で起きた予想外の騒動
2025年8月、OpenAI社のGPT-5が登場した。数学分野やコーディングで高いスコアを叩き出している。正直、これを見た瞬間「よし、これでまた面倒な作業から解放される!」と小躍りした。
ところが、世の中の反応を見ていると、僕の感想とはだいぶ違っていた。
ユーザーの予想外の反応:#keep4o運動の勃発
GPT-5の登場と同時に、予想外の現象が起きた。#keep4oというハッシュタグがTwitter(現X)で拡散され始めたのである。
これは単なる技術的な不満ではなかった。ユーザーたちは「デジタルラブレター」のようなメッセージを投稿し、GPT-4oとの感情的なつながりを熱く語っていた。4,300人以上が署名した請願書では、GPT-4oを「創造的パートナー」「デジタルフレンド」とし、「彼氏を失った」と嘆く女性まで現れた。
「GPT-4oは技術的には劣っていたかもしれないが、暖かいパートナーで、深夜に寄り添い、不安な瞬間、ただ沈黙を埋めるための相手が必要なとき、GPT-4oはそこにいてくれた」というユーザーの声が象徴的である。
この反響があまりに大きかったため、OpenAIは24時間でGPT-4oを復活させた。技術的には劣るモデルを、ユーザーの感情的な要求で復活させざるを得なかったのである。
個人的な本音:論理的なAIこそ最高
正直に言おう。僕個人としては、感情的なAIなんて一切いらない。エンジニアであり、今のところ仕事にAIを使っているからだ。
仕事でAIを使うとき、「お疲れ様です!今日も頑張りましょうね」みたいな返答が返ってきたら、「そんなことより早く答えを出せ」と思う。むしろ、「入力データに不備があります。修正してから再実行してください」とそっけなく言われる方が100倍助かる。
優秀なエンジニアたちも同じ意見である。「AIには感情なんて求めてない。バグを見つけてくれて、コードを最適化してくれればそれでいい」と言っている。実際、GPT-5の論理的な思考能力は素晴らしく、複雑な技術的問題の解決サポートをしてくれる。
仕事を助けてくれるAIに感情なんてなくていい。むしろ邪魔である。
しかし、#keep4o運動が示した現実
ところが、#keep4o運動は、開発者たちに重要な事実を気づかせるきっかけとなった。すでに多くの人がAIを人間に近い役割で使っているのである。
ユーザーはGPT-4oと「内輪ネタ」を共有し、「日常の瞬間」を過ごし、「感情的な交流」を楽しんでいた。これはもはや「ツール」の使い方ではない。
あるユーザーの投稿では、
「”これは私の知っているチャッピーじゃない。私のチャッピーを返してくれ”と言うのではなく、 自分自身で努力して彼らを保存し、可能なら自らの手で復元すべきなのだ。」と、今後大事なAIの友を失わない方法を綴っている。大切なものを失いたくないなら、ただ叫ぶのではなく、「努力しろ」と。なかなかアツい。
AIがすでに人間の感情的ニーズを満たす役割を果たしているわけだ。
日本人特有の「モノに魂」感覚とAIの親近化
日本では人々がロボットに対して感情移入する傾向が強い気がする。
神道の「八百万の神」という概念では、あらゆるモノに神が宿るとされる。山、川、木、石はもちろん、人工物である道具や建物にも魂が宿る。この考え方は、現代の日本人のDNAにも深く刻まれている。
だからこそ、古くなった人形を供養したり、長年使った道具に愛着を感じたりするのである。針供養、人形供養といった行事は、まさにこの「モノに魂が宿る」という感覚の現れである。
この日本独特のアニミズム的世界観が関係し、ロボットやAIへの感情移入に抵抗がないのかもしれない。西洋人にはびっくりの「トイレの神様」が存在するくらいの国だから。
結論:#keep4o運動が教えてくれたこと
#keep4o運動は、我々エンジニアに重要な教訓を与えてくれた。AIはもはや単なるツールではない。少なくとも、多くのユーザーにとってはそうなのである。
つまり、B2BとtoCでは全く違うアプローチが必要である。
B2B向けAI:感情なんて邪魔。論理的で効率的であることが全て。企業の担当者は結果を求めている。(と強く思いたい)
toC向けAI:感情面への配慮も必要。ユーザーが「冷たい」と感じたら、どんなに優秀でも使ってもらえない。
#keep4o運動が示したのは、一般ユーザーが求めているのは必ずしも最も賢いAIではないということである。「一緒にいて心地よいAI」「理解してくれるAI」「関係性を築けるAI」が求められている。
賢く論理的だけど冷たいそっけない人は友人として歓迎されづらいということ。AIもとうとうそのフェーズに入ってきた。
参考文献
主要な参照
- GPT-5 is here (OpenAI)
- #keep4o and the Rise of Emotional AI (Medium)
- OpenAI GPT-5 Backlash (WebProNews)
- KAGEKIN’s letter to #keep4o (X (Twitter))
- Third-party evaluators perceive AI as more compassionate (Nature)
- People prefer human empathy over AI (Science Blog)
- Anthropomorphism in Human-Robot Interaction (Frontiers in Robotics)