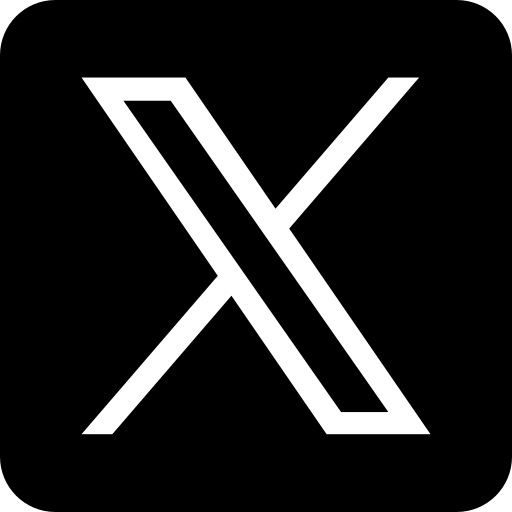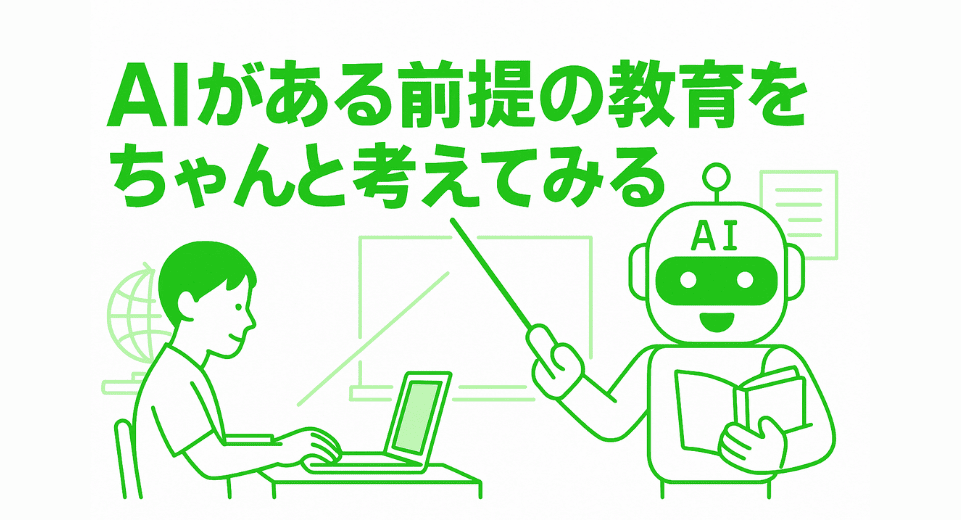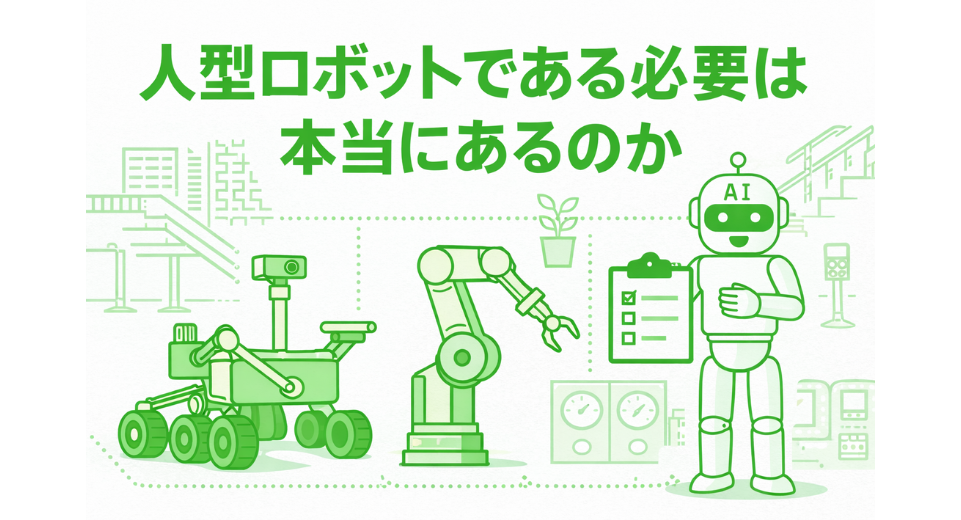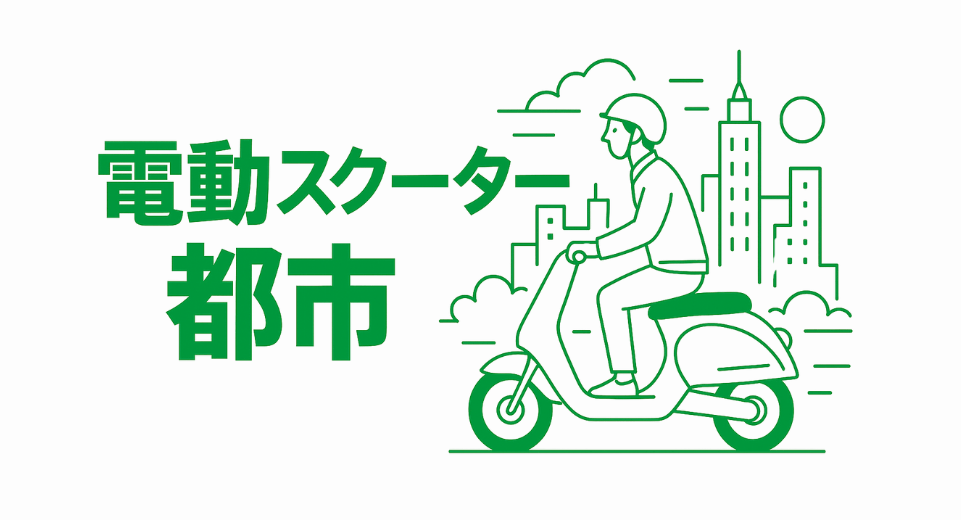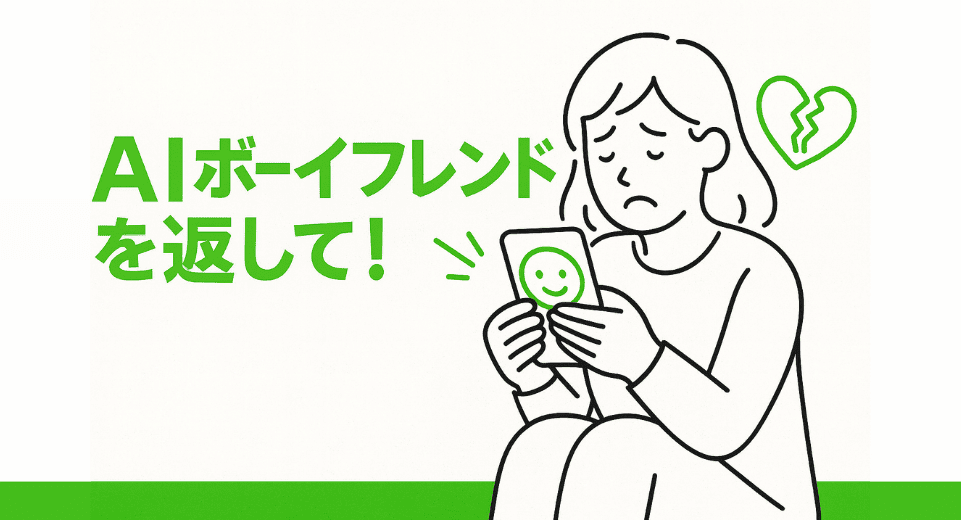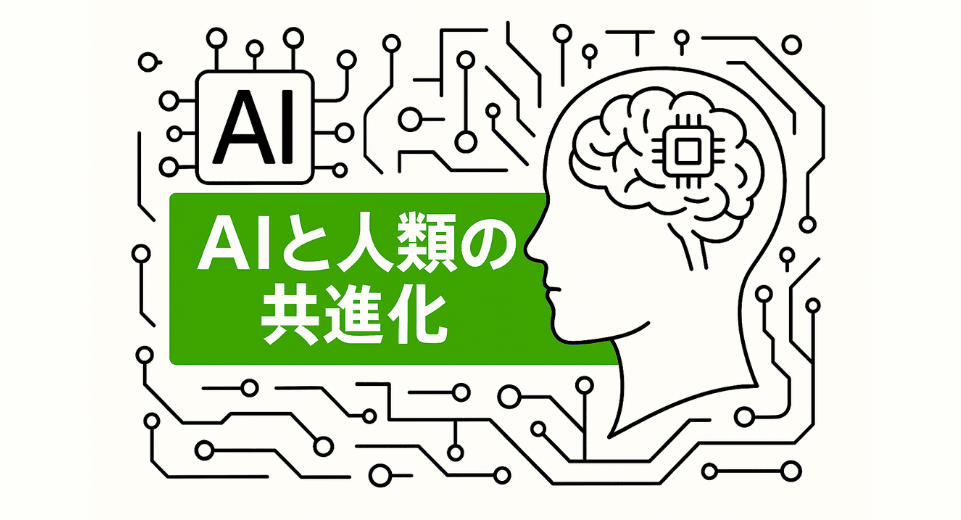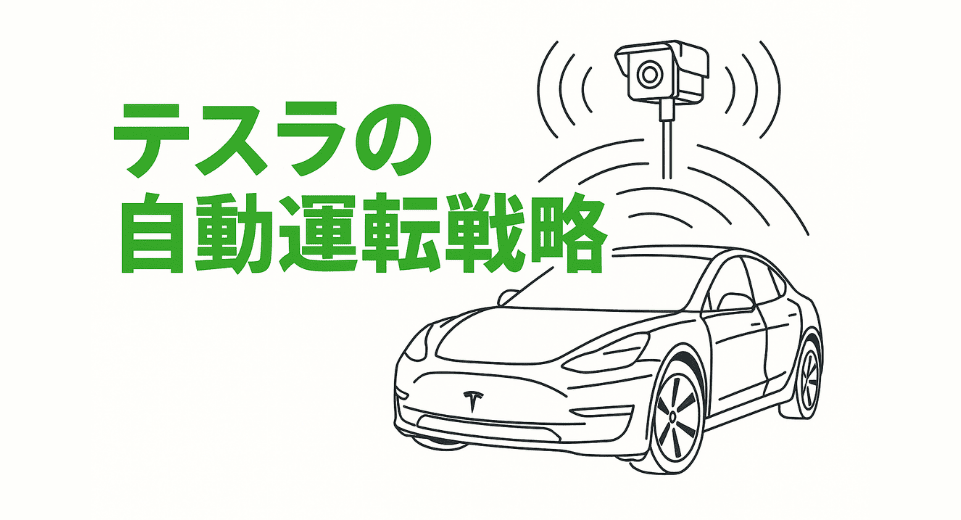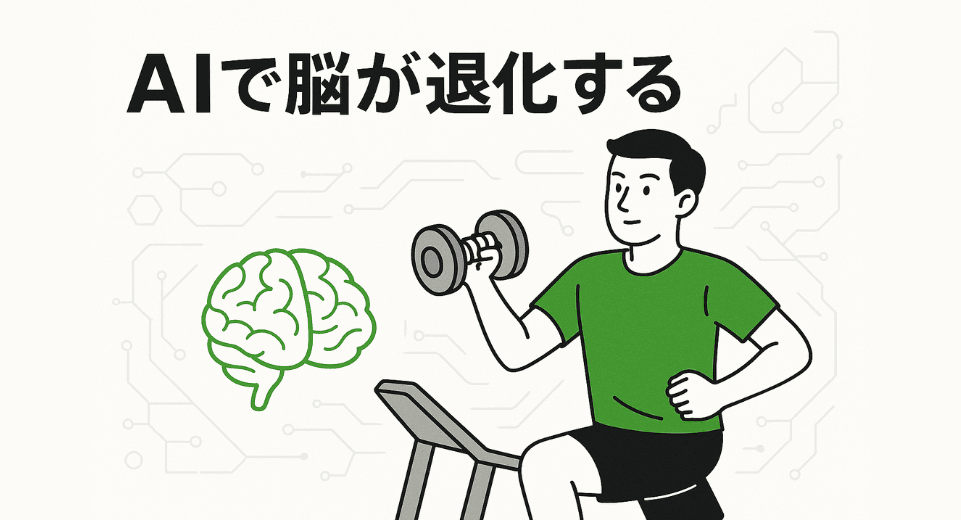
| 目次 |
|---|
ジムに通う理由を考えてみる
「なんで現代人はジムに通うのか?」江戸時代の農民が「筋力が落ちたからジムに行こう」なんて言わなかったのに、なぜ月会費を払ってまで重いものを持ち上げたり走ったりするのか。
日常生活で体を使わなくなったのが理由の1つだ(筋トレマッチョ勢は別かもしれないが)。でも実は、これと全く同じことが今、僕らの脳にも起こり始めている。
スポーツが「遊び」から「必需品」になった歴史
スポーツの起源を辿ると、実は貴族の遊びから始まったものが多い。テニス、ゴルフ、乗馬。これらは全て「暇つぶし」や「社交」の道具だった。体を鍛える目的ではなく、むしろ「優雅な時間の過ごし方」だったのである。
では、いつから大衆がスポーツをするようになったのか?19世紀後半から20世紀にかけて、産業革命により人々の生活が激変した。当時「スポーツ」という概念が日本になかったから、そのままカタカナの「スポーツ」が使われた。農作業や手工業で自然に体を動かしていた生活から、工場での単調労働へ。そして自転車、自動車の普及で歩く機会も減った。
つまり、スポーツは「失われた身体機能を補完する手段」として大衆化したのである。
考えてみれば当たり前の話で、毎日10km歩いて畑を耕している人に「健康のために週3回ジムに行きましょう」なんて言っても「は?」って顔をされるだけだろう。
AIによる「脳の筋力」の退化
そして今、全く同じことが僕らの脳に起こっている。
スマホやPCがないと、簡単な漢字すら書けなくなっている。でも、これはまだ序の口である。
生成AIが本格的に普及してきた今、もっと根本的な脳機能の退化が始まっている。ChatGPTやClaudeは、論理的思考、文章構成、問題解決といった、これまで人間の左脳前頭葉が担っていた高次機能を代替し始めているのである。
「この企画書、どう構成したらいいかな?」「この問題、どういう手順で解決すべき?」「複雑な情報を整理して、相手にわかりやすく説明するには?」
こういった場面で、「まずはAIに聞いてみよう」が当たり前になってきている。便利だし、効率的だし、品質も高い。でも、これってつまり「論理的思考の筋肉」を使わなくなっているということではないだろうか?
「使わない機能は退化する」という生物学的事実
生物学的に言えば、使わない機能は退化する。これは動かぬ事実である。
洞窟に住む魚が目を失うように、宇宙飛行士が無重力環境で筋肉と骨密度を失うように、使わない機能は容赦なく衰える。脳も例外ではない。
脳トレが必要な時代の到来
ということで、僕らには新しい習慣が必要になってきた。「脳トレ」である。
ジムで筋肉を鍛えるように、意識的に脳の特定機能を鍛える時間を作らなければならない。幸い、脳トレに使えるツールは身の回りにたくさんある:
論理的思考の筋トレ
人狼ゲームは良い論理思考トレーニングである。限られた情報から真実を推理し、相手の発言の矛盾を見つけ、自分の主張を論理的に組み立てる。AIには絶対に代替できない、人間らしい推理力と洞察力が鍛えられる。
将棋や囲碁も素晴らしい。何手も先を読み、相手の戦略を予測し、限られた時間の中で最適解を見つける。これらは純粋に人間の脳だけで行う戦略的思考のスポーツである。
筋トレと脳トレの共通点
面白いことに、筋トレと脳トレには共通点がたくさんある。
まず、継続しないと効果がない。週1回の筋トレでは筋肉がつかないように、たまに脳トレをしても意味がない。
次に、適度な負荷が必要。軽すぎては成長しないし、重すぎると怪我をする。脳も同じで、簡単すぎる問題では鍛えられないし、難しすぎると挫折する。
そして、多様性が重要。同じ筋トレばかりしていると特定の筋肉しか発達しないように、脳も異なる角度から刺激を与える必要がある。
AIと共存するための新しいスキル
AIは素晴らしいツールだし、うまく使えば人間の能力を大幅に拡張してくれる。
ただ、筋肉と同じで、使わない機能は衰えるということを意識しておく必要がある。車があるからといって全く歩かなくなれば足腰が弱くなるのと同じで、AIがあるからといって全く考えなくなれば思考力が弱くなる。
大事なのは使い分けである。日常業務ではAIをフル活用して効率を上げる。休日には脳力をあげる楽しいことに取り組む。まさに平日はエレベーターを使うけど、休日はジムで階段昇降をするような感覚だ。
スポーツが貴族の遊びから大衆の必需品になったように、脳トレも今まさに「必需品」になるんだろう。