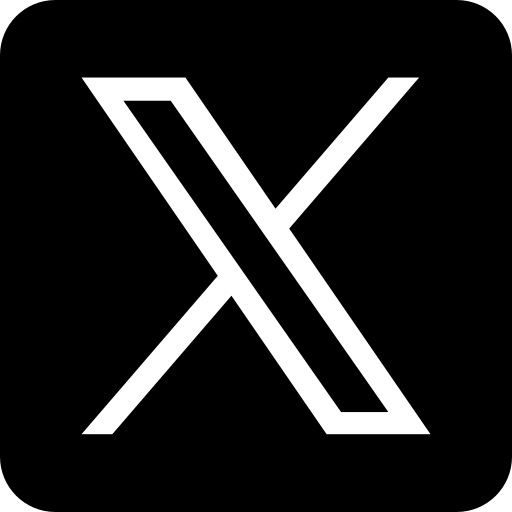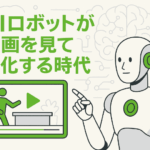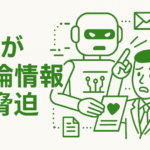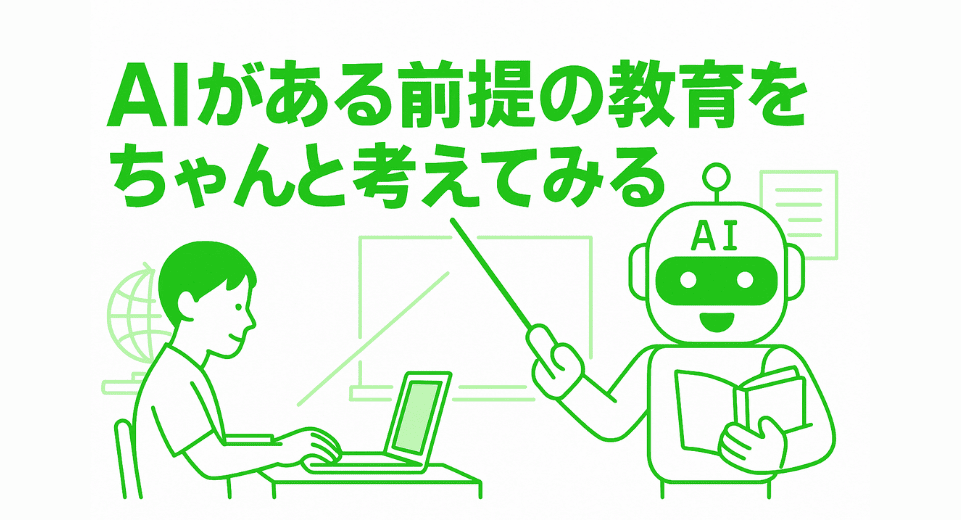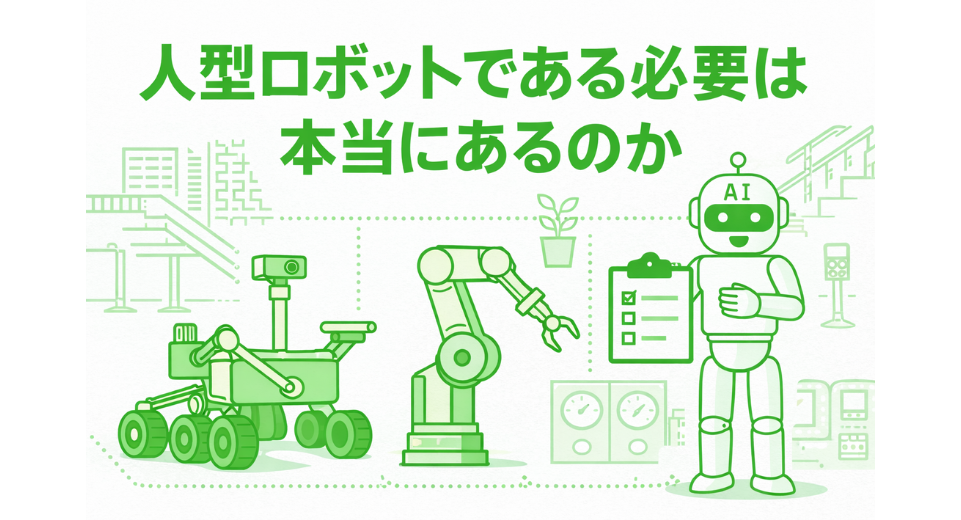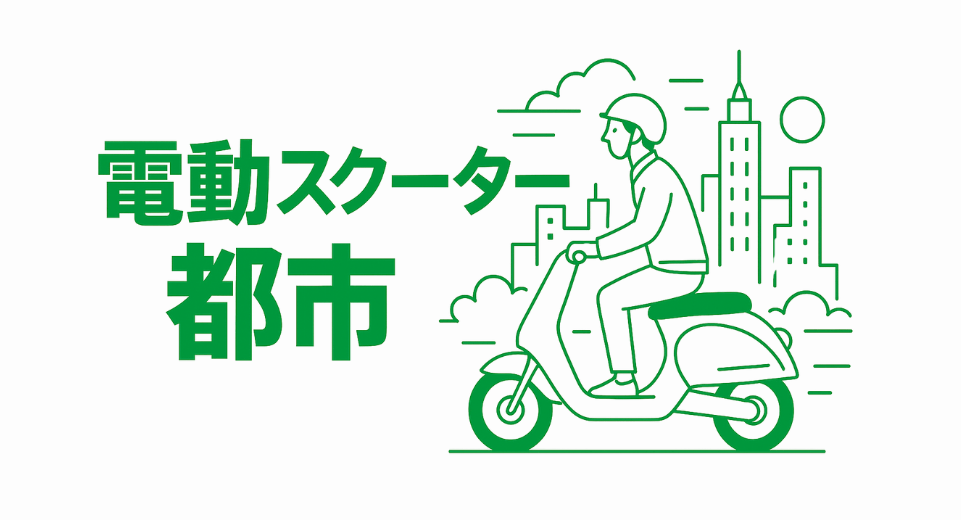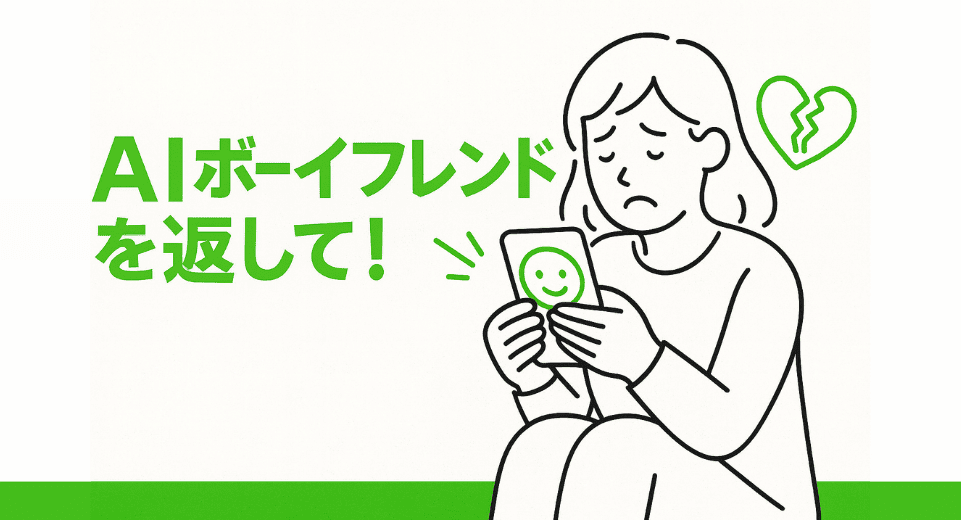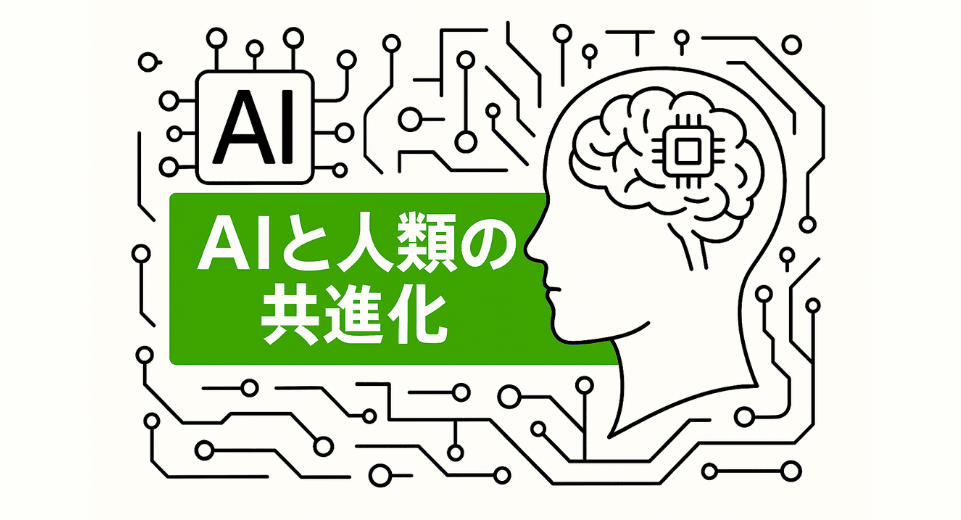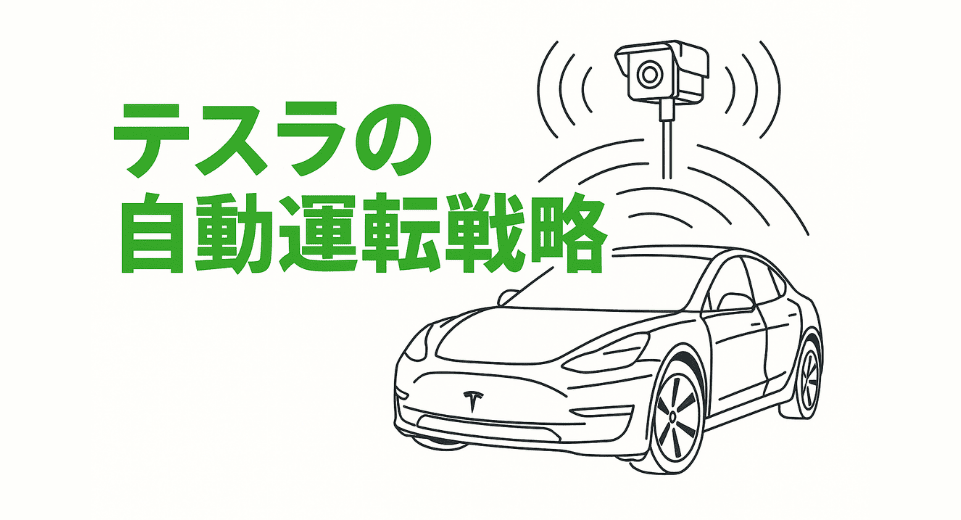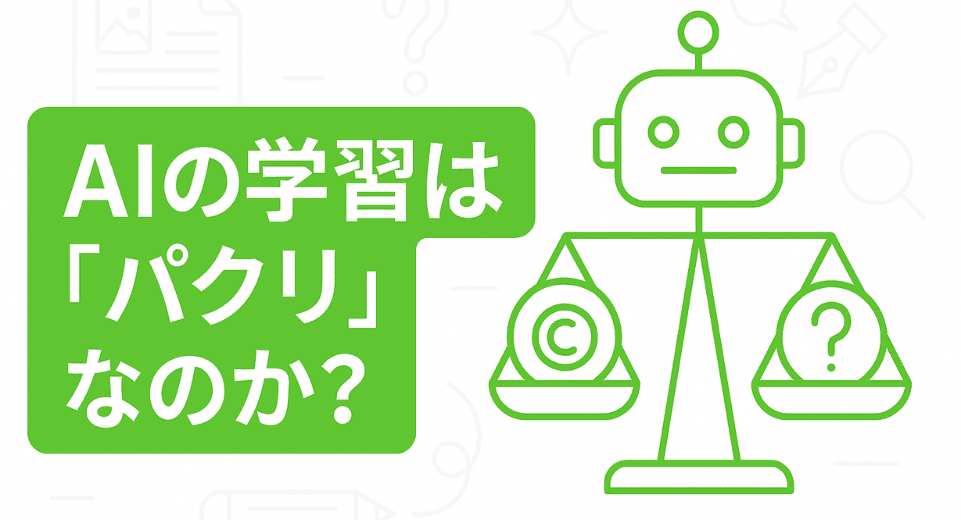
| 目次 |
|---|
「そもそもAIの創作は人間の著作物から学習して作ったものだから、著作権侵害ではないか?」
この疑問は、誰しもが抱く現実的な懸念である。しかし、判例を詳しく調べていくと、この議論の本質は私たちが思っているより複雑で興味深い。
導入:AIか人間か、もはや見分けがつかない現実
先日、面白い出来事があった。2023年、ドイツの写真家ボリス・エルダグセン氏がAIで生成した作品「Pseudomnesia: The Electrician」でソニー世界写真賞のクリエイティブ部門を受賞したのである。しかし彼は自らAI生成であることを明かし、受賞を辞退した。
この事件の衝撃的な点は、プロの審査員でさえAI生成画像を本物の写真として評価してしまったということである。つまり、技術はすでに「誰が作ったのか」を判別不可能なレベルに達している。
では、このAIの学習行為は果たして著作権侵害なのだろうか?
AIの学習は”フェアユース”:最新判例が示す新たな常識
2025年6月、この問題に決定的な法的判断が示された。まず、6月24日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のウィリアム・オルサップ判事は、Anthropic社がClaude AIの訓練のために著作権で保護された書籍を使用した行為について「フェアユース(公正利用)」に該当すると認めた(NPR)。
興味深いのは判事の論理である。オルサップ判事は「”Everyone reads texts, too, then writes new texts”(人間は誰でもテキストを読み、そして新しいテキストを書く)」と述べ、「”Like any reader aspiring to be a writer, Anthropic’s LLMs trained upon works not to race ahead and replicate or supplant them — but to turn a hard corner and create something different”(作家志望の読者と同様に、AnthropicのLLMは作品を先取りして複製したり置き換えたりするために学習したのではなく、大きく方向転換して何か違うものを創造するために学習した)」と判断した(Publishers Weekly)。
翌日の6月25日には、同じ裁判所でMeta社のLlamaというAIモデルに関する訴訟でも、チャブリア判事が同様にフェアユースを認める判決を下した(Fortune)。
人間とAIの学習プロセス:本質的に同じである
これらの判決が示すのは、AIの学習と人間の学習を法的に区別しない立場である。人間もまた、無数の著作物を読み、観て、聞いて学習し、その上で新たな作品を創造している。
たとえば、小説家は先行作品を大量に読んで着想を得るが、いちいち権利処理をしない。画家はルーブル美術館で名画を見て技法を学ぶが、著作権料を支払わない。音楽家は他の音楽を聞いて影響を受けるが、それは創作の自然なプロセスとして受け入れられている。
AIが行っているのも、本質的には同じプロセスである。既存の作品からパターンを学習し、新しい作品を生成する。判事が「高度に変容的(transformative)」と評価したのは、AIが単純にコピーするのではなく、学習を通じて新しい表現を生み出しているからである(Goodwin Law)。
ただし、データ取得方法には要注意
興味深いのは、Anthropic社の判決では海賊版からのデータ取得については著作権侵害と認定されたことである(XenoSpectrum)。つまり、AIの学習行為自体は合法だが、学習データの取得方法が違法であれば問題となる。
これは企業にとって重要な示唆である。AIを活用する際は、適法に取得したデータを使用することが不可欠である。
AIがもたらすクリエイティビティの革命
エルダグセン氏の事例に戻ろう。彼は「AIは写真ではない」と明言し、「プロンプトグラフィ」という新しい表現形式だと主張した(CGWORLD)。この発言は重要な洞察を含んでいる。
将棋や囲碁の世界で人間がAIに勝てなくなったように、創作の世界でも純粋に人間のみが行う創作と、AI支援による創作を分ける必要が出てくるだろう。しかし、将来的には多くの人々がAIによって生み出された創作物を楽しむことになるのは間違いない。
クリエイティビティの本質が変わる
人間はクリエイティビティを特別で高尚なものとして捉えがちである。しかし、AIが示す現実は、クリエイティビティの本質の一つが自分自身の欲求や満足を満たすことにあることを浮き彫りにしている。
これまでクリエイティビティは他者に価値を提供することが主な目的と捉えられてきたが、AIの登場によって、実は自己表現や自己満足という側面も本質的な要素だったことが明らかになった。
ビジネスにおけるデザインとアートの分化
ビジネスの世界で求められるクリエイティビティは、アートよりもデザインに重きを置く傾向がある。デザインは他者に対して価値を提供する手段として機能し、AIはこの領域で大きな力を発揮する。
一方で、アートは自己表現の側面が強く、今後はビジネスにおけるデザインと、個人的な表現としてのアートがより明確に分かれていくだろう。現代のデザイナーがアート的要素を取り入れがちな傾向に対し、AIは純粋なデザインとしての価値提供に特化することで、より大きなインパクトをもたらす可能性がある。
特にアートの世界では、多くの人々が作品が誰によって生み出されたのかというストーリーを価値判断の重要な要素とする。人間が生み出したからこそ感じられる独自の価値や、その背景にある物語に重きを置く声は根強く残るだろう。
結論:AIは人間の創作と同じ学習の延長線上にある
法的な観点から見れば、AIの学習プロセスは人間の学習プロセスと本質的に変わらず、フェアユースとして認められる方向性が示されている。つまり、「AIが人間の著作物から学習すること」自体は著作権侵害ではない。
重要なのは、適法に取得したデータを使用し、AIの出力が原著作物の単純な複製ではなく変容的であることである。企業がAIを活用する際は、この境界線を明確に理解し、適切なガイドラインを策定することが不可欠である。
AIと人間のクリエイティビティは対立するものではなく、それぞれの強みを活かしながら共存し、新たな価値観や可能性を生み出していく時代がすでに始まっているのである。
参考文献
米国AI著作権判例
- メタ、AI著作権訴訟で勝訴──フェアユース該当も限定的 | WIRED.jp
- 「生成AIの学習に書籍を無断使用」は合法───米地裁「フェアユース」 Anthropicへの訴訟巡り – ITmedia NEWS
- 大規模言語モデルのAnthropic、著者団体との訴訟で米連邦裁判所が「AI学習はフェアユース」と初判断
- 米・著作権訴訟でAnthropicの「フェアユース」を認定も海賊版利用を断罪:AI業界の未来と倫理の境界線 | XenoSpectrum
AI写真コンテスト事例
- 世界的な写真コンテストの入賞作はAIが作ったものだった…作者は受賞を辞退「議論を始めたかった」 | Business Insider
- AI生成画像で世界最高峰の写真コンテストを受賞した孤高のアーティスト。写真界の異端児に独占インタビュー
- 国際的写真コンテストでAI画像が優勝 「主催側にAIを受け入れる準備があるか試した」 作者は受賞拒否 – ITmedia NEWS