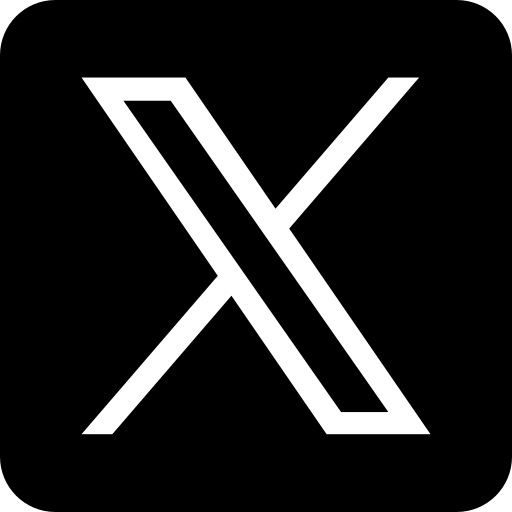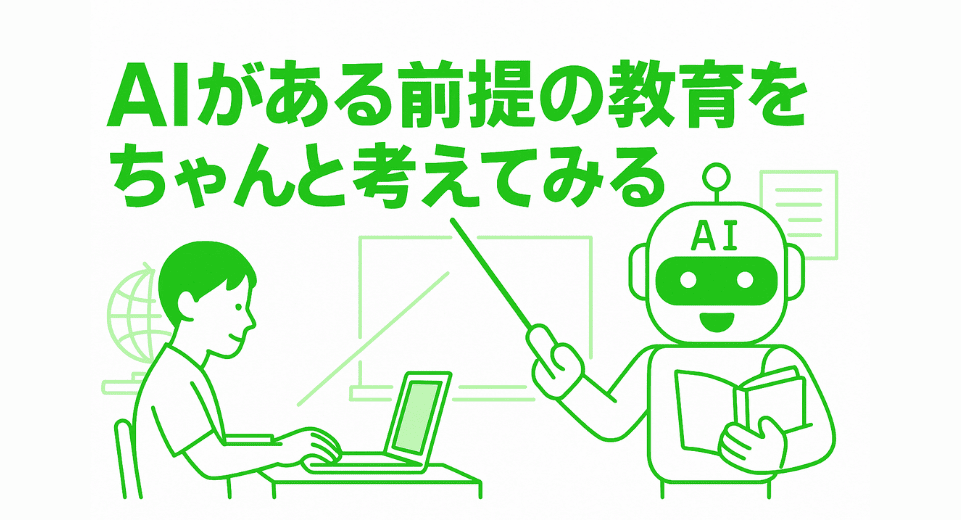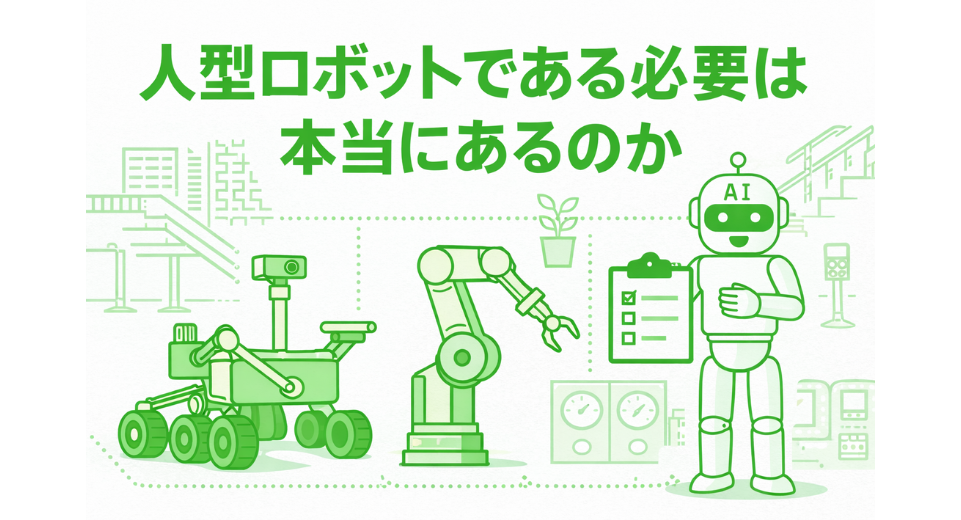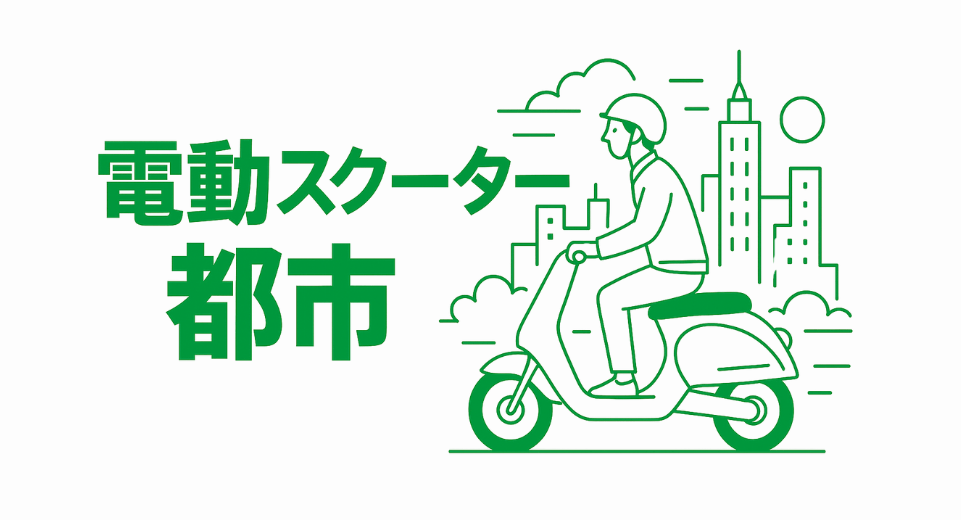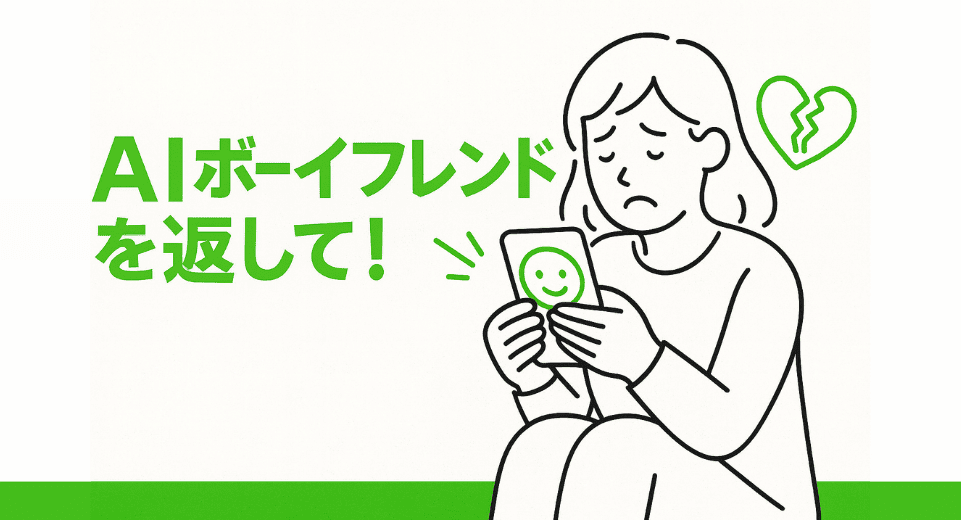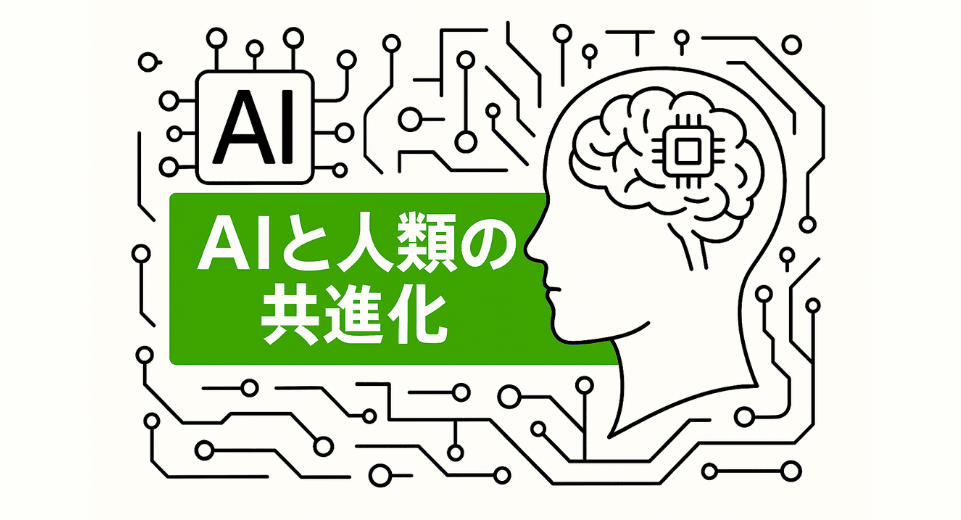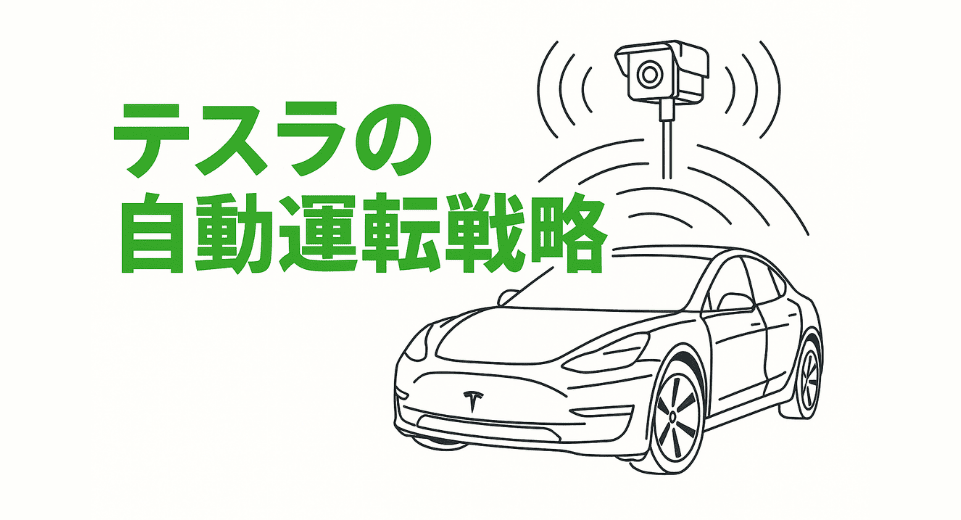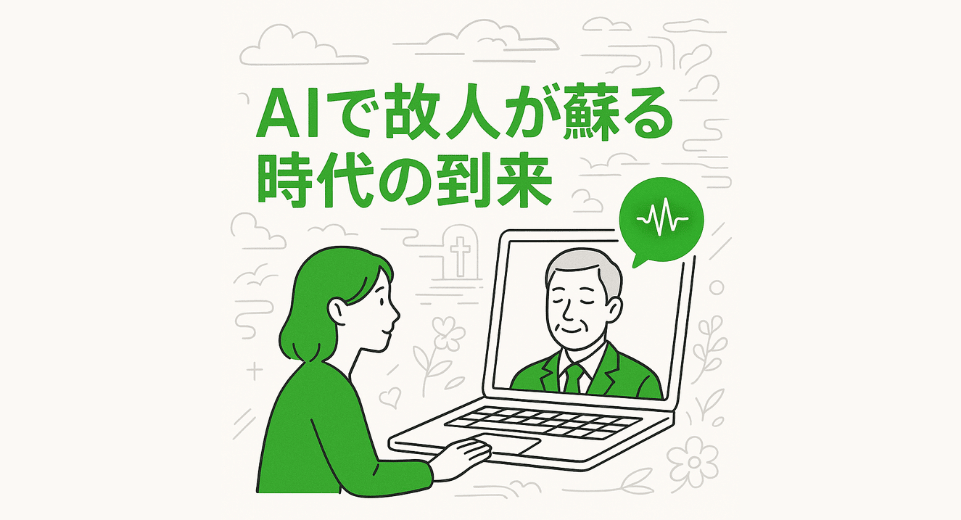
| 目次 |
|---|
AIで故人が蘇る時代の到来
最近、中国などで人工知能(AI)を使い、故人のアバターを生成するビジネスがブームになっているという話題が日本でも注目を集めている。実は、この仕組みを知れば知るほど、以前書いたLLMの技術と同じような話だということがわかってくる。要するに、「適当に次の言葉を選んでいるだけ」である。ただし、今度は故人が言いそうな言葉を選ぶわけだ。
中国で巻き起こる故人復活ブーム
中国の伝統的な祝日「清明節」を前に、中国のネットユーザーの間で故人を人工知能(AI)技術でよみがえらせる「AI復活」に注目が集まっている。価格もわずか10元(約210円)から1万元(約21万円)までと幅広い。
中国のデジタルヒューマン市場は2022年、120億元(約2600億円)規模に成長し、25年までには4倍増が予想されている。これはもはや実験レベルの話ではない。リアルなビジネスである。
特に興味深いのは、このビジネスが中国の伝統的な文化に深く根ざしているという点だ。中国の家庭では、親族が亡くなった後、数年間その人の肖像画を飾るのが一般的である。また、毎年4月の清明節には祖先の墓を掃除し、線香を燃やして過去1年間の出来事を報告するという、死者との一方向の対話文化が古くから存在している。
つまり、技術が先行したのではなく、元々あった文化的ニーズに最新のAI技術が追いついたということである。
技術の仕組み:データが人格を作る
故人復活サービスの基本的な仕組みは、想像しているよりもシンプルである。
- 音声データの収集:故人の声を録音したデータを集める
- 画像・動画の学習:写真や動画から表情や動きを抽出
- テキストデータの分析:メールやSNSの投稿から口調や考え方を学習
- AIモデルの構築:これらのデータから「その人らしさ」を再現
必要なデータ量はサービスによって異なるが、故人を紹介する文章は最大50万字以下の文章が目安とされている。つまり、小説一冊分程度の情報があれば、その人らしい会話を再現できるということだ。
ただし、ここで重要なのは「再現」であって「復活」ではないということである。AIが学習するのは、あくまで故人が残したデータのパターンなのだ。
世界各国で始まっている故人サービス
この分野は中国だけの話ではない。
アメリカ:HereAfter AI
アメリカ・カリフォルニア州のスタートアップ企業HereAfter(ヒアアフター)は、故人が生前に録音した音声やデバイス上のメール、テキストメッセージなどをAI処理することによって「バーチャルな故人」を生成するサービスを提供している。料金はおよそ1か月あたり20ドル(約3000円)前後と比較的リーズナブルである。
日本:TalkMemorial.ai
日本でも株式会社ニュウジアがTalkMemorial.aiという故人の声や思い出をAIで再現し、ご家族やご友人との対話を叶える新しい追悼体験を提供するサービスを開始している。「大切な人との声や姿を、永遠に」をコンセプトに、心のつながりを未来へつなぐという思想が興味深い。
技術的には最新の生成AIを活用し、リップシンクや表情をリアルタイムで再現できるという。
僕が感じる技術の可能性と限界
実際に調べてみて感じたのは、この技術は「思い出を呼び起こすツール」として優秀だということである。完璧な故人の再現ではなく、遺族が故人との思い出を振り返るきっかけを提供している。
「ほぼ毎日『デジタルおじいちゃん』とおしゃべりをして、気持ちが和らいだ」という体験者の声があるように、心理的なサポートとしての効果は確実にある。
しかし同時に、「死というものの尊さを薄めよう、目をそらそう、否定しようという、そこはかとない虚しさ」を感じるという専門家の意見もある。技術が進歩しても、死という現実は変わらないのだ。
倫理的な課題という大きな壁
この分野には技術的な課題以上に、倫理的な問題が横たわっている。
まず、故人の同意の問題がある。生前に本人が明確に許可していない場合、遺族が勝手にAI故人を作成することは適切なのだろうか?
次に、データの所有権である。故人のSNSの投稿や写真は誰のものなのか?家族であっても無断使用は問題ないのか?
また、AI故人の発言内容も重要な問題だ。故人が生前に言わなかった内容をAIが生成した場合、それは故人の意思と言えるのだろうか?
AIは死を克服するのか?
結論から言うと、AIで人は死ななくならない。少なくとも、現在の技術では。
AIが再現できるのは、故人が残したデータのパターンでしかない。記憶も、感情も、魂も、AIは再現できない。できるのは「その人らしい反応」を模倣することだけである。
しかし、それでも価値はある。遺族にとって、故人との思い出を鮮明に保つ手助けをしてくれるからだ。「AIは喪失の痛みを消し去ることはできませんが、思い出をいつまでも残すことは間違い無くできる」という表現が的確だと思う。
技術と向き合う僕たちの姿勢
今回この記事を書くために色々調べていて、改めて思ったのは、技術そのものに善悪はないということである。問題は、その技術をどう使うかだ。
故人復活AIも、使い方次第では遺族の心を癒す素晴らしいツールになるし、使い方を間違えれば死者の尊厳を傷つける危険なものにもなる。
重要なのは、技術の可能性と限界を正しく理解し、適切なガイドラインの下で活用することだ。特に、故人の同意の問題や、遺族の心理的な依存の問題については、十分な配慮が必要だろう。
死とテクノロジーの未来
AIが発達しても、人間は死ぬ。しかし、死の意味は変わるかもしれない。
昔は、死ねば全てが終わりだった。今は、デジタル上に残されたデータが故人の痕跡を留めている。そして将来は、AIが故人との擬似的な対話を可能にする。
必要なデータは僕のスマホに入っているデータで十分すぎる。LINE、メール、スケジュール、Googleマップのお気に入り、写真、動画。他の人もほぼ一緒なはずだ。なんなら、死んだあとで僕の代わりにソーシャルメディアにそれっぽい写真を合成して投稿することだって朝飯前。良いのか悪いのかは自分自身で決めれば良い