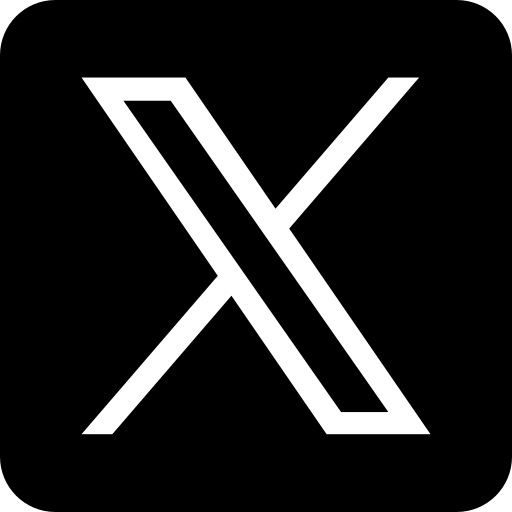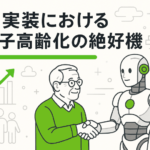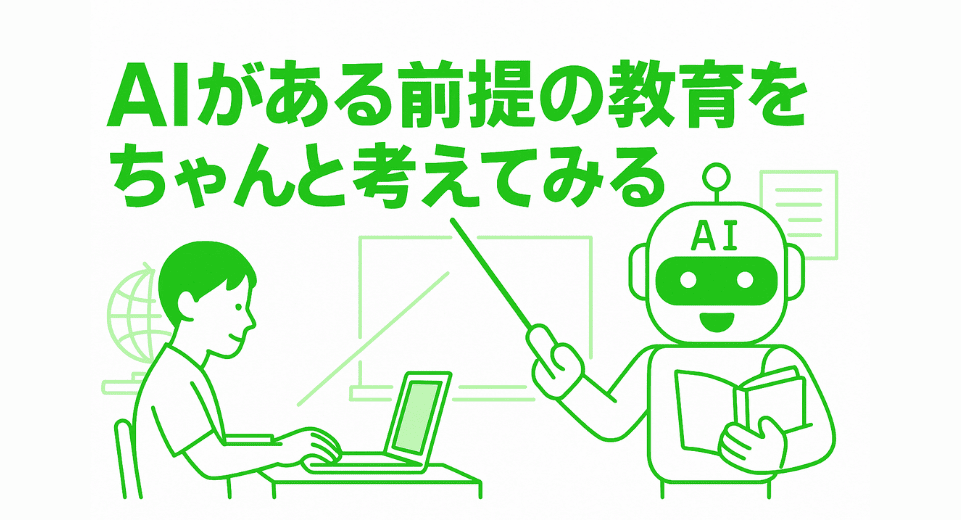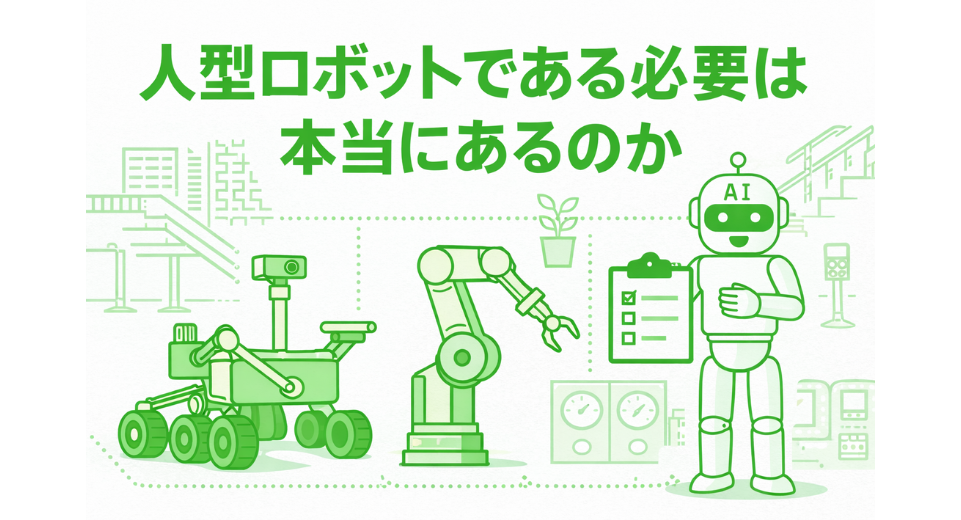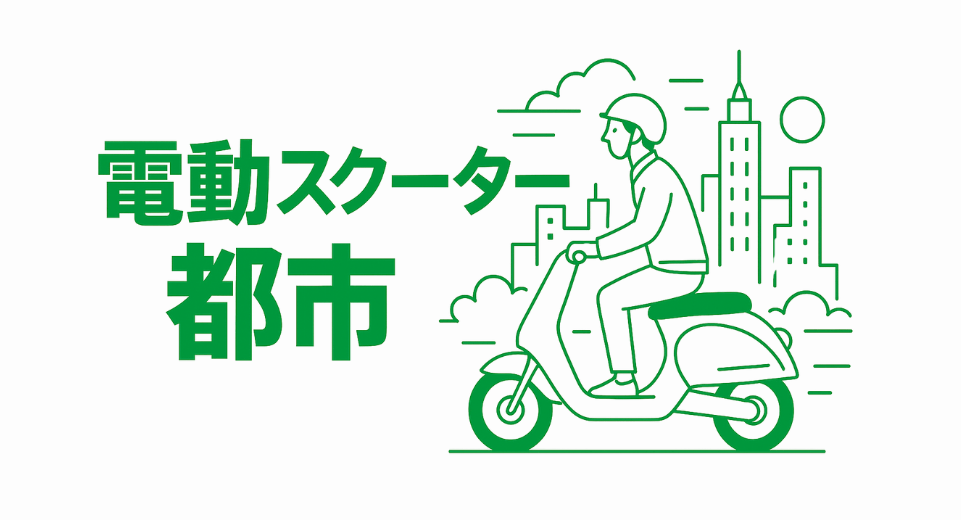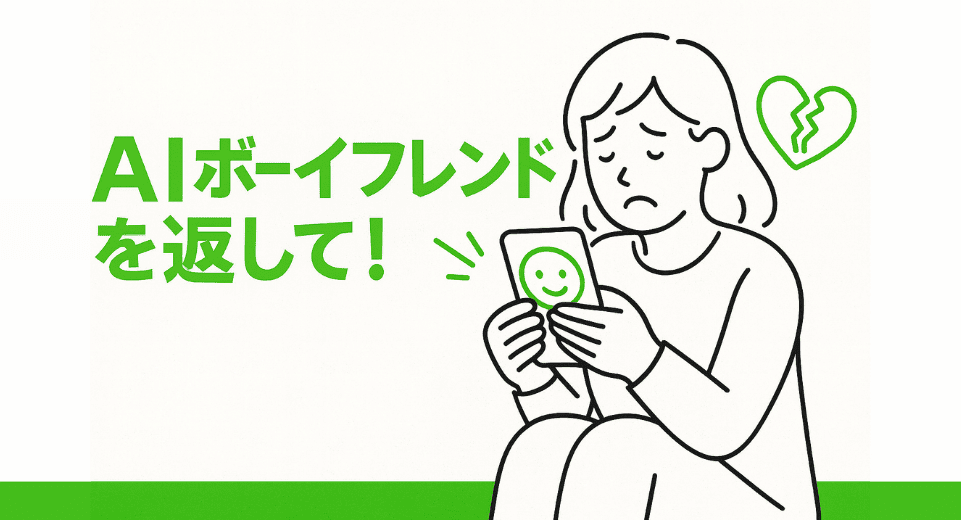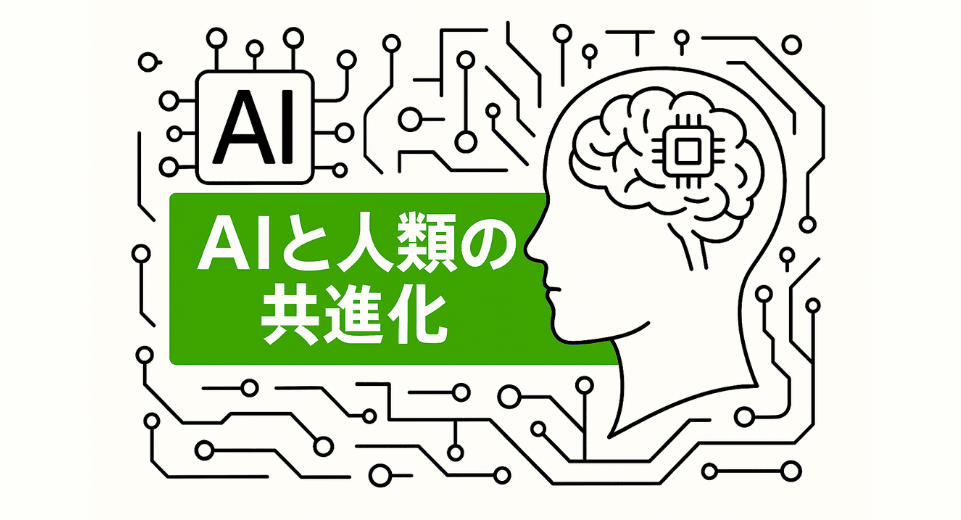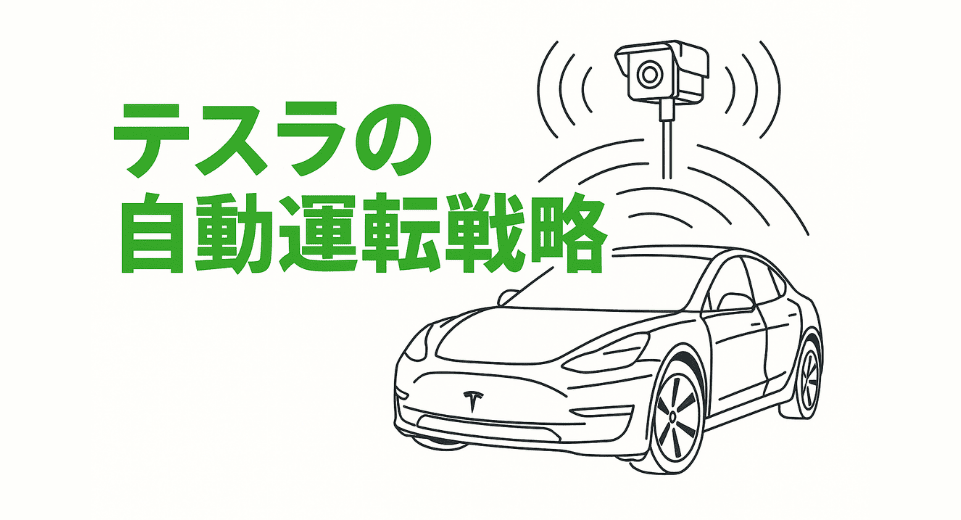| 目次 |
|---|
議事録を取る人がいなくなった日
最近、Web・対面を問わず、ミーティングは基本的に録音している。議事録はAIにまとめさせる。議事録を取る人がいらなくなったのである。
参加者全員が議事録作成という作業から解放され、100%打ち合わせの内容に集中できるようになった。これは単なる効率化の話ではない。僕らとAIの関係が根本的に変わってきているということなのである。
AI音声入力の現状日本語の問題
僕はPC、スマホでAI音声入力を多用している。圧倒的に早いからである。特に書くことが決まっている場合は爆速だ。「句点」「読点」「かっこ」「かっことじ」「中黒」と言えば、ちゃんと変換してくれる。
iPhoneもMacも、過去に使った固有名詞を学習して候補に出してくれる。キーボードでのタイピングができない若者、スマホのフリック入力の方が早いという世代がすでにいる。さらにその先には、音声入力のみの若者たちが当然出てくる。
ただし、現状の問題は、日本語には同音異義語が異常に多いということである。
「こうせい」と言っても、「校正」「構成」「厚生」「公正」「更正」などがあり、AIが混乱してしまう。英語などの他の言語よりも同音異義語が日本語では圧倒的に多い。
これに気づいてから、音声入力する際に意識的に同音異義語を避けるようになった。
- 言い換え例:「文章の校正」ではなく「原稿チェック」と言う
AIを前提とした話し方の変化
議事録をAIで作成させることを前提に、僕は話し方も変えた。具体的には、最後に今日のまとめ、TODO事項などをわかりやすく繰り返すようにしている。
「今日のまとめです。新機能の仕様は来週までに確定。開発開始は再来週から。担当は田中さん。以上です。」
こんな感じで、AIが議事録を作りやすいように意識的に整理して話すのである。つまり経験の浅いスタッフが議事録を作る場合と同様だ。
シンプリファイドイングリッシュという先例
実は、このような考え方には先例がある。「シンプリファイドイングリッシュ」という概念である。
これは、航空宇宙産業や製造業の技術文書において、翻訳の精度を高め、理解の誤りを防ぐために開発された英語の書き方ルールである。複雑な構文を避け、一文を短くし、専門用語を統一するなど、機械翻訳にも人間にも理解しやすい英語を書くためのガイドラインだ。
機械が理解しやすい言語は、結果的に人間にとっても理解しやすいのである。
「AIフレンドリージャパニーズ」という新しい作法
僕が実践しているのは、AIに理解されやすい日本語で話すということである。これを「AIフレンドリージャパニーズ」と呼んでいる。これも現状のAIファーストの考え方の一つだ。
議事録はAIに書かせる、入力はAI音声入力を使う、という前提で既存のやり方を見直す。議事録ぐらい人が書けば良いじゃないかと考えるかもしれないが、すべての打ち合わせの議事録を記憶し、すべての仕様書を熟知し、数十万行のソースコードを把握するAIに勝てるはずがない。
近い内にこれらの情報を把握し、打ち合わせに参加者として同席し、そのAIの意見を聞く状況がすぐに来る。そんなAIを僕らは作り始めている。APIを組み合わせれば基本的には成り立つので難しい話ではない。
実は、これは過渡期の話
ただし、AIにわかりやすい用語を使って入力させるのは、AIに割り当てられるメモリが限られているうちだけだ。これは単にリソースの問題なので、十分なリソースがあれば、AIは多くのコンテキスト情報を把握でき、同音異義語も問題なく把握する(前後の文をすべて把握すれば、どう変換すればよいかわかる)。人間ができているのだからできないわけがない。
つまり、いずれはAIの方が僕らの曖昧な日本語を理解してくれるようになる。「あれ、どうなってる?」「例の件は?」みたいな曖昧な表現でも、過去の会話履歴や資料を参照して理解してくれる時代が来る。
僕らが準備すべきこと
じゃあ、僕らは何を準備すればいいのか?
まずは、AIと一緒に働くことを前提とした仕事のやり方を身につけることである。議事録はAIに任せ、音声入力を活用し、AIが理解しやすい指示の出し方を覚える。
すべてを把握したAIに打ち合わせに同席させる、ボットで答えてもらえる仕組みを作る。
最後に、変化を恐れずに新しいツールを試すことである。完璧を求めず、まずは使ってみる。