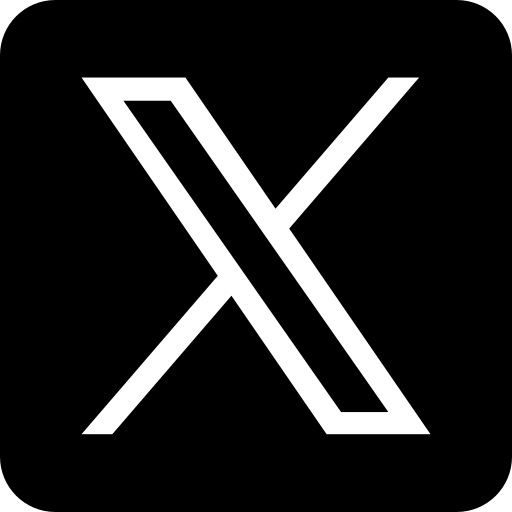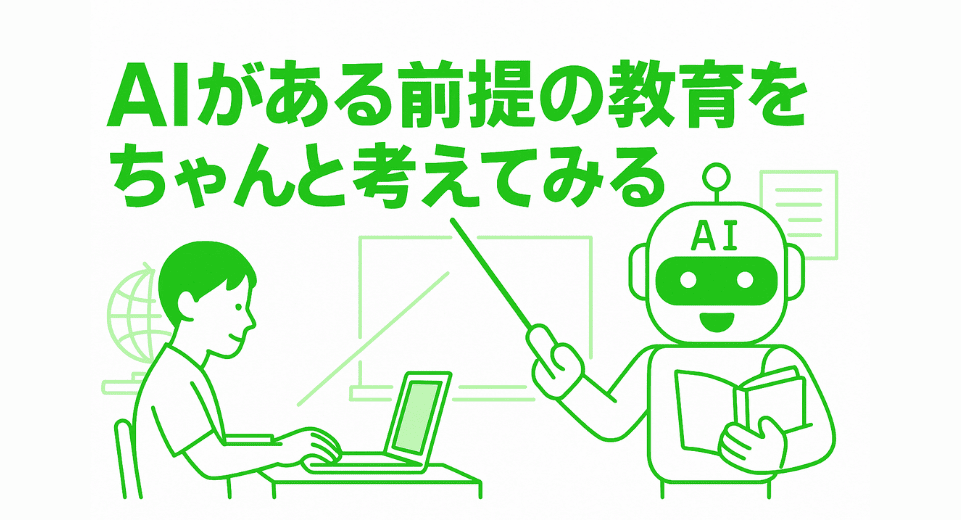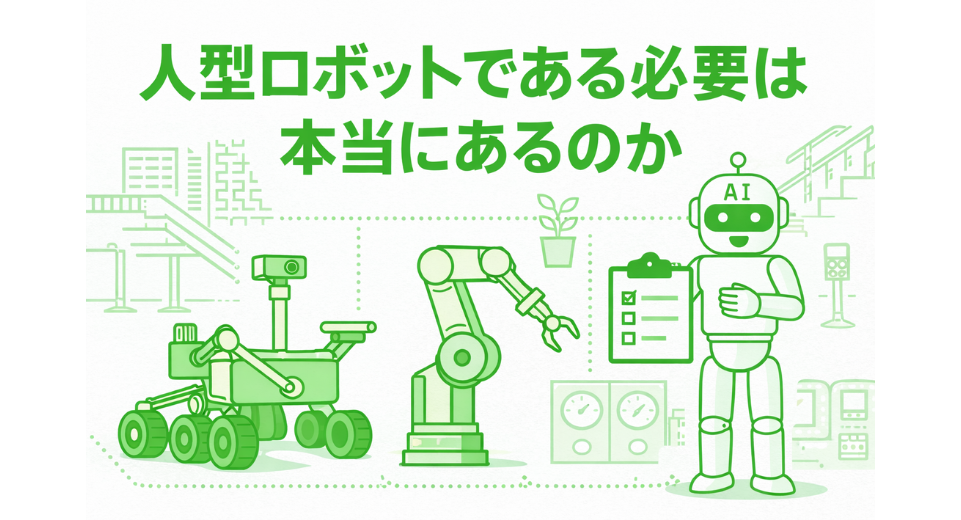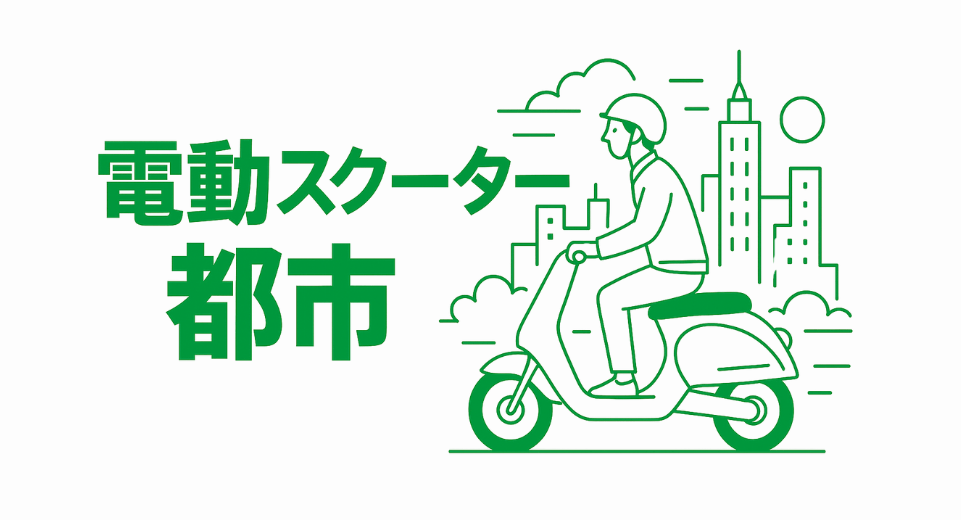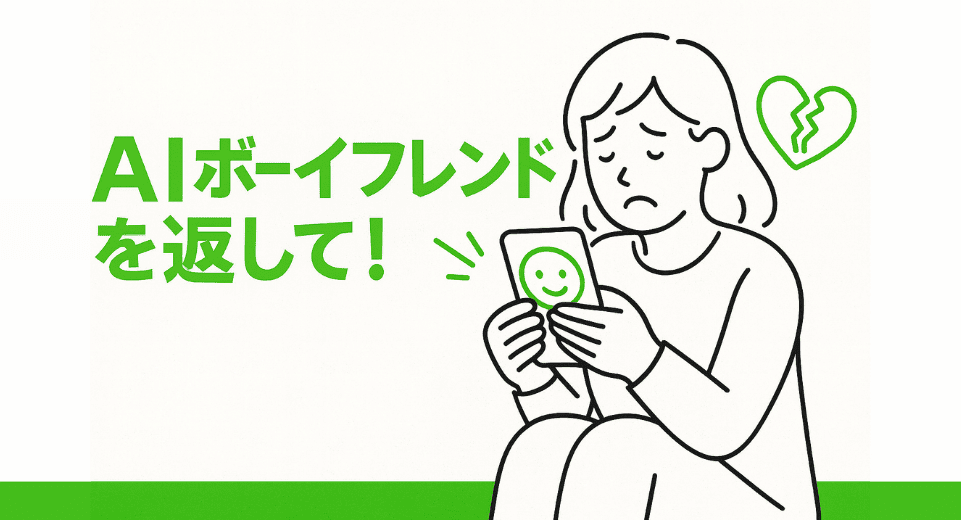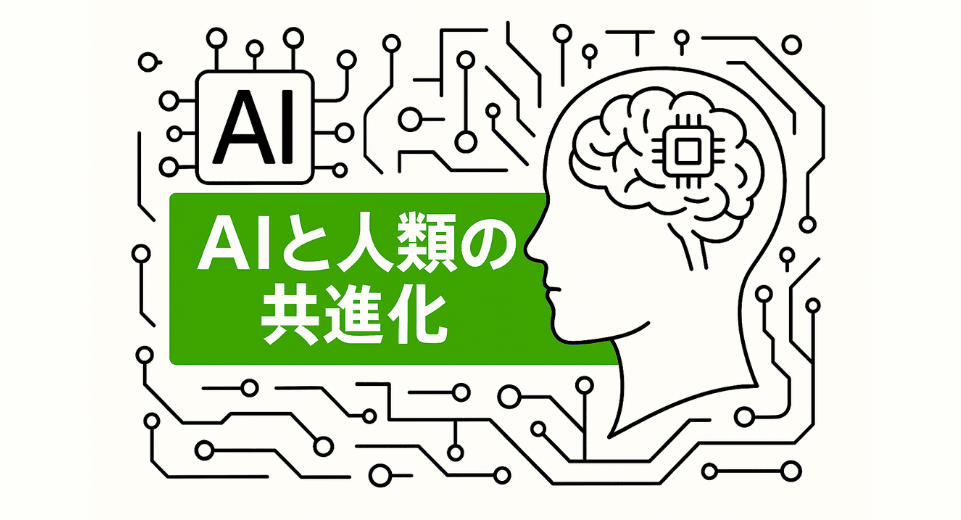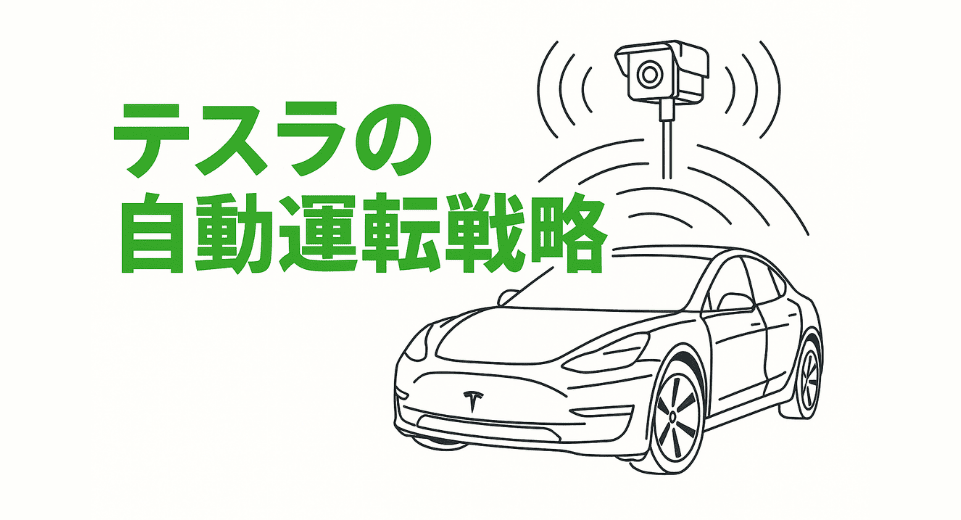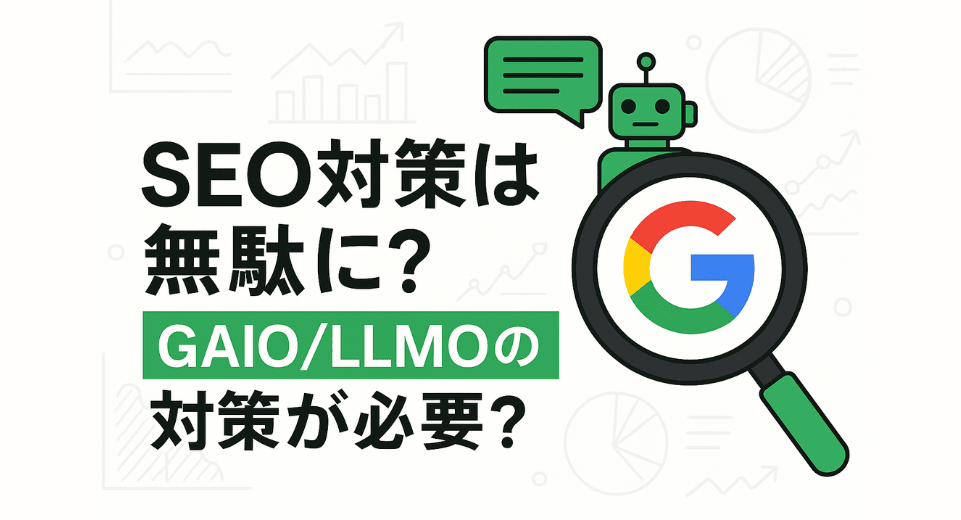
| 目次 |
|---|
Google AI Overviewとは何か
Google AI Overview(AIO)は、2024年から本格展開されたGoogleの新機能である。これは検索結果の最上部に、AIが複数のウェブページから情報を収集・要約した回答を表示するシステムである。
従来の検索では、ユーザーは複数のサイトを訪問して情報を収集する必要があった。しかしAI Overviewでは、「仙台の紅葉のピークはいつ頃ですか?」と検索すると、複数の観光サイトや気象データから情報を抽出し、「仙台の紅葉は例年10月下旬から11月上旬にピークを迎えます」といった形で、まとめられた回答が表示される。
この機能は現在、200以上の国と地域で展開されており、特に情報収集型の検索クエリで積極的に表示されている。
数字で見る衝撃的な変化
実際のデータを見ると、AI Overviewの影響の深刻さがよくわかる。
クリック率(CTR)の大幅減少
まず、CTR(Click Through Rate:クリック率)について説明しておこう。これは検索結果が表示された回数のうち、実際にクリックされた割合を示す指標である。例えば、検索結果が100回表示されて10回クリックされた場合、CTRは10%となる。ウェブサイトへの流入を測る最も重要な指標の一つである。
複数の調査機関が、AI Overviewによる深刻なトラフィック減少を報告している。
Ahrefsの調査では、AI Overviewが表示される検索において、検索結果1位のサイトでも34.5%のCTR減少が確認されている。これは30万キーワードを分析した包括的な調査結果である。
Amsiveの調査では、平均的に15.49%のCTR減少が観測されている。特に深刻なケースでは、フィーチャードスニペットと組み合わさった場合に37.04%もの減少が記録されている。
最も衝撃的なのは、MailOnlineの事例である。同社のCarly Steven氏の警告によると、Google AI Overviewsがトラフィックに劇的な影響を与え、検索トラフィックは避けられない減少に向かうとしており、実際に56%ものCTR減少が報告されている。
ゼロクリック検索の増加
BrightEdgeの最新データが示すのは、検索行動の根本的な変化である。検索表示回数は前年比49%増加している一方で、実際のクリック率は30%減少している。
つまり、人々はより多く検索しているが、サイトを訪問する頻度は大幅に減っているのである。これが「ゼロクリック検索」と呼ばれる現象で、ユーザーが検索結果ページで情報を得て、サイトを訪問せずに満足してしまう状況を表している。
参考文献:
- Google AI Overviews are hurting click-through rates (Search Engine Land)
- New Google AI Overviews data: Search clicks fell 30% in last year (Search Engine Land)
- Shocking 56% CTR drop: Google AI Overviews gut MailOnline’s traffic (Search Engine Land)
AI時代の新戦略:GAIO/LLMOの台頭
この変化に対応するため、新しい最適化手法が注目されている。
GAIO(Generative AI Optimization)の必須化
GAIOは、AIの回答生成プロセスに最適化する手法である。従来のSEO(検索エンジン向け)から、AIによる引用・参照を目的とした戦略への転換が求められている。
成功事例として:
- 構造化データ(Schema.org)の強化:AIの情報抽出効率を向上させる
- 権威性構築:専門家インタビューや学術データの明示により信頼性を高める
LLMO(Large Language Model Optimization)の具体的手法
LLMOは、大規模言語モデルに最適化された新しいアプローチである。具体的には以下の手法が効果的である:
- コンテキストウィンドウ対策:AIが処理できるトークン数内で、簡潔かつ高密度な情報を提供する
- エンティティ最適化:キーワードより「企業名・製品名」などの実体(エンティティ)を明確に定義する
- マルチモーダル対応:音声・画像検索向けに、alt属性の詳細化やQ&A形式コンテンツを増強する
AI検索時代には、クリックされることよりも「言及されること」が重要になる。ChatGPTやPerplexityなどのAIプラットフォームで自社ブランドが情報源として引用されるよう、LLMO を意識した対策が必要である。
LLMO実践手法:
- 権威性の構築:業界専門家として認知されるよう積極的に発信
- 構造化データの強化:AIが理解しやすい形式での情報提供
- 専門コンテンツの作成:独自研究や業界レポートの公開
- ブランド監視:AIプラットフォームでの自社言及状況の把握
マルチモーダル検索への対応
検索はテキスト中心から音声や画像を組み合わせたマルチモーダル検索へと進化している。Googleレンズやマルチサーチの普及により、画像とテキストの連携が検索流入増加のカギとなっている。
多様な検索形式への対応策:
音声検索最適化
- 自然なQ&A形式のコンテンツ設計
- 会話調の文章構成
- 「近くの〇〇」といったローカルクエリへの対応
画像検索最適化
- alt属性の詳細な記述
- 画像周辺のテキスト強化
- 高品質で情報価値の高い画像の提供
動画コンテンツ
- 文字起こしテキストの掲載
- チャプター分けによる構造化
- キーモーメントのマークアップ
将来的に本当にそうなのか?
と教科書的に言われているAI時代への対策を上記に書いてみた。個人的にはこれには大きな疑問を抱く。
そもそも「AIに選ばれてなにか意味があるのか?」
検索エンジンの結果で上の方にAIが回答を完璧に出してくれたら、その引用サイトにそもそも誰も訪れない。
- そもそもWebブラウザで人はいつまで検索するのか。特に疑問形の検索に対しては、アプリに聞いてしまえば終了になる可能性が将来的には高い。
- AIがもっと進化すれば複数のサイトの情報などをまとめて回答を出すわけだからいつまで引用サイトをAIが出し続けるのかは疑問
- 多くのブログコンテンツ等がAIによって生成されWebにはゴミのような情報が今後どんどん増える。ゴミコンテンツが増えれば増えるほど、AIにまとめてもらったものだけを人間が読むようになる。
あるブランドや企業名を認知してもらい、そこが発信しているものを読みに来る人のためのWebは残るが、これまでのWebマーケのように、お役立ち情報のような記事を量産するSEO対策をして、ユーザーのクリックを誘導し、コンバージョン(成約)に結びつけるというビジネスは早めに衰退する。プッシュ型の広告等で認知してもらい、Webを訪れてもらうという流れは引き続き残るだろう。